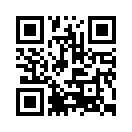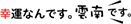マイナンバー(社会保障・税番号制度)についてマイナンバー(社会保障・税番号制度)の概要について説明します。
 マイナンバー(社会保障・税番号制度)とは
マイナンバー(社会保障・税番号制度)とは
マイナンバー(個人番号)は、住民票を有するすべての方に1人1つの番号(12桁)を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
マイナンバーは一生使うものです。マイナンバーが漏えいして、不正に使われるおそれがある場合を除いて、一生変更されませんので、大切にしてください。
注意
マイナンバー制度をかたり、全国では預金口座番号など個人情報を聞きだそうとする不審な電話や訪問があったとの相談が寄せられています。預金口座番号や個人情報を電話や訪問でお聞きすることはありませんのでご注意ください。
マイナンバーの活用で期待されている効果としては、大きく3つあげられます。
- 1.行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間で連携が進み、手続きが正確でスムーズになります。
- 2.添付書類の削減など、行政手続きが簡素化され、住民の負担が軽減します。行政機関が持っている自分の情報の確認や、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ることも可能になります。
- 3.所得や行政サービスの受給状況を把握しやすくなり、負担を不当に免れたり、給付を不正に受けたりすることを防止するほか、本当に困っている人にきめ細かな支援を行えるようになります。
マイナンバーが必要となるとき
社会保障、税、災害対策の行政手続きで必要になります。
たとえば、
- (1)年金の手続き
- (2)健康保険を受給しようとするとき
- (3)児童手当の出生および転入に伴う新規申請をするとき
- (4)所得税および復興特別所得税の確定申告をするとき
- (5)税や社会保障の手続きで、勤務先や金融機関に提示するとき
といった場面でマイナンバーを提示することになります。
マイナンバーは社会保障、税、災害対策の中でも、法律や自治体の条例で定められた行政手続きでしか使用することはできません。
1.マイナンバー確認と本人確認の実施について
マイナンバー制度の開始に伴い、本人確認が厳格化されます。これは、なりすまし、虚偽、不正届出の防止と個人情報の保護のための措置ですので、ご理解とご協力をお願いします。
また、社会保障・税の手続きについては、申請書類などへマイナンバーを記入して頂くことになり、マイナンバー確認のため通知カード、又は個人番号カードの提示が必要となります。
通知カードをお持ちの場合
通知カード

■個人番号の確認に利用するカードです。
■行政機関の窓口手続きでマイナンバーの提示と本人確認が必要な場合には、カードのほか、身元確認ができるもの(免許証、パスポートなど)が必要です。
 本人確認できるもの
本人確認できるもの
- 1点でよいもの(顔写真があるもの)
- 運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、障がい者手帳、療育手帳、在留カード、特別永住証明書など
- 2点以上の提示が必要なもの
- 各種保険証(国民健康保険被保険者証、健康保険被保険者証、船員保険被保険者証、介護保険被保険者証、共済組合員証)、年金手帳、年金証書、恩給証書など
個人番号カードをお持ちの場合
個人番号カード ※希望者に対して交付(申請が必要です)

■個人番号を記載した書面を提出するさまざまな場面で、身分証明書として利用するカードです。
■行政機関の窓口手続きでマイナンバーの提示と本人確認が必要な場合には、このカード1枚でOKです。
代理人の方が手続きされる場合
代理人の方が申請される場合は、代理人の本人確認を行い、申請者との関係を委任状等により確認します。
- <手続きに必要なもの>
- (1)代理人の本人確認できる書類
- (2)申請者のマイナンバーカード又は通知カードの写し
- (3)委任状(同一世帯の方が代理人の場合必要ありません)
個人番号カードについて
「個人番号カード」は、表面に氏名、住所、生年月日、性別と本人写真が表示され、裏面にマイナンバーが記載されます。個人番号カードは、本人確認のための身分証明書として使えるほか、各種サービスに利用できます。(必要な方のみ申請してください。)
ICチップについて
個人番号カードにはICチップが付属しており、カードに記載されている情報のほか、電子申請のための電子証明書が記載されますが、所得の情報や病気の履歴などのプライバシー性の高い個人情報は記録されません。そのため個人番号カードからすべての個人情報が分かってしまうことはありません。
住民基本台帳カード(住基カード)との違いについて
住民基本台帳カードは利用期限まで利用できますが、その後は利用できなくなります。また個人番号カードとの重複所持はできません。
個人番号カードと住民基本台帳カードの違い
| 項目 | 個人番号カード | 住民基本台帳カード |
|---|---|---|
| 申請 | 郵送 | 市役所、総合センター |
| 交付 | 住所地区の総合センター | 市役所、総合センター |
| 発行 | 平成28年1月から | 平成27年12月まで |
| 手数料 | 無料(紛失等による再交付は有料) | 500円(電子証明書は別途500円) |
| 有効期間 | 発効日から10回目の誕生日 (20歳未満は5回目の誕生日) |
発効日から10年 |
| 電子証明書 | 標準搭載 5回目の誕生日まで有効 |
希望者のみ発行 発効日から3年間有効 |
マイナンバーの確認が必要な主な手続き
平成28年1月より、社会保障・税の手続きの際にマイナンバー(社会保障・税番号)の確認と、本人確認が必要となりました。
市役所・総合センターでの社会保障・税の手続きの際には、マイナンバーの確認できる書類(「通知カード」又は「個人番号カード」)と本人確認のできる書類(免許証など)を忘れずにお持ちください。
マイナンバーの確認が必要な主な手続きについては以下のとおりです。
| 区分 | 手続き | お問合せ |
|---|---|---|
| 住民票・戸籍 | ・転入・転居・転出などの異動 ・戸籍届出の氏名などの変更 |
市民生活課 電話0854-40-1031 |
| 区分 | 手続き | お問合せ |
|---|---|---|
| 国民健康保険 | ・資格の取得・喪失 ・被保険者の氏名、世帯、住所、世帯主の変更 ・被保険者証の再交付 ・療養費、特別療養費、移送費、高額療養費、高額介護合算療養費の支給申請 ・第三者行為による被害の届出 ・限度額適用認定、特定疾病給付対象療養に係る認定の申請 |
市民生活課 電話0854-40-1031 |
| 後期高齢者医療 | ・資格の取得・変更・喪失 ・被保険者証の再交付 ・基準収入額適用申請 ・基準収入額適用申請 ・療養費、特別療養費、高額療養費の支給申請 ・特定疾病認定、特定疾病療養受療証再交付の申請 ・限度額適用・標準負担額減額認定、認定証再交付の申請 |
市民生活課 電話0854-40-1031 |
| 区分 | 手続き | お問合せ |
|---|---|---|
| 児童手当 | ・児童手当・特例給付の認定請求 ・児童手当・特例給付の別居監護申立 |
市民生活課 電話0854-40-1031 |
| 児童扶養手当 | ・認定請求 ・額改定請求 |
子ども家庭支援課 電話0854-40-1067 |
| 障がい者福祉 | ・身体障がい者手帳の申請 ・療育手帳の申請 ・精神障がい者保健福祉手帳の申請 ・特別障がい者手当、特別障がい児手当、福祉手当の申請 ・自立支援医療に関する申請 ・障がい児通所支援の給付申請 ・補装具費の支給申請 ・特別児童扶養手当の認定・額改定請求、所得状況届 |
長寿障がい福祉課 電話0854-40-1042 |
| 生活保護 | ・生活保護の申請 | 健康福祉総務課 電話0854-40-1041 |
| 区分 | 手続き | お問合せ |
|---|---|---|
| 市民税 | ・市町村民税・道府県民税の申告 ・給与支払報告書の提出 ・給与所得者異動の届 ・軽自動車税減免の申請 |
税務課 電話0854-40-1034 |
| 固定資産税 | ・固定資産税減免の申請 ・償却資産に関する申告 |
税務課 電話0854-40-1034 |
| 区分 | 手続き | お問合せ |
|---|---|---|
| 介護保険 | ・資格の取得・異動・喪失 ・被保険者証等の再交付 ・住所地特例の適用・変更・終了の届 ・高額介護サービス費の支給申請 ・負担限度額認定証の申請 ・基準収入額適用の申請 |
長寿障がい福祉課 電話0854-40-1042 |
| 区分 | 手続き | お問合せ |
|---|---|---|
| 子ども子育て | 幼稚園・保育所・認定こども園の入所申込み | 子ども政策課 電話0854-40-1044 |
※上記の手続き以外にもマイナンバーが必要になる場合があります。
マイナンバー独自利用について
マイナンバー独自利用とは
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律により、マイナンバーを利用することができる事務が定められていますが、法に定められていない事務については自治体の条例に規定することで、その事務(独自利用事務)に限りマイナンバーを利用することができます。
独自利用事務の情報連携に係る届出について
マイナンバー独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、個人情報保護委員会に届け出て承認されています。
また、この情報連携する独自利用事務の届出書については個人情報保護委員会により公表されています。
情報連携する独自利用事務の届出書はこちら![]() で確認できます。
で確認できます。
個人情報保護のため、ご理解とご協力をお願いします。
法人番号について
法人にも13桁の法人番号が指定され、広く公開されます。個人番号とは異なり、誰でも自由に利用することができます。
マイナンバーについてさらに詳しい情報は下記ホームページまで。コールセンターも開設しています。
マイナンバー制度のよくある質問(FAQ)や最新情報は、内閣府のマイナンバー(社会保障・税番号制度)のホームページに掲載してあります。個人情報保護委員会、総務省、国税庁、厚生労働省等の特設サイトへもリンクしています。「マイナンバー」で検索してください。
デジタル庁のマイナンバー(社会保障・税番号制度)ホームページ![]()
マイナンバーについてご不明な点がある方や、さらに詳しい情報を知りたい方は、お気軽にお問合せください。
【マイナンバー総合フリーダイヤル】
 電話番号
電話番号
- 0120-95-0178(無料)
 開設時間
開設時間
- 平日 9時30分から20時00分まで
- 土日祝 9時30分から17時30分まで(年末年始除く)
一部IP電話等で上記ダイヤルにつながらない場合(有料)
マイナンバー制度、マイナポータルに関すること 050-3816-9405
「通知カード」「マイナンバーカード」または、「紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止について」 050-3818-1250
英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応
マイナンバー制度、マイナポータルに関すること 0120-0178-26
「通知カード」「マイナンバーカード」または、「紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止について」 0120-0178-27
 お問い合わせ先
お問い合わせ先
- 市民環境部 市民生活課
- 〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1 - Tel 0854-40-1031
- Fax 0854-40-1039
- shiminseikatsu@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。

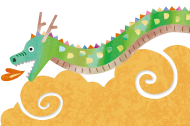

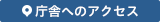

 妊娠・出産
妊娠・出産 子育て
子育て 学校・教育
学校・教育 結婚・離婚
結婚・離婚 住まい・引越し
住まい・引越し 就職・退職
就職・退職 高齢者・介護
高齢者・介護 お悔やみ
お悔やみ









 お問い合わせはこちら
お問い合わせはこちら