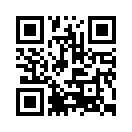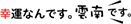第三セクター等調査特別委員会(最終報告)第三セクター等調査特別委員会(最終報告)についてのページです。
 第三セクター等調査特別委員会(最終報告)一覧
第三セクター等調査特別委員会(最終報告)一覧
報告日 平成18年9月5日
調査・審査事項等
第三セクター等調査特別委員会最終報告
- 第1 はじめに(特別委員会の調査・研究方針)
- 1.調査・研究の基本的方針
第三セクターを取り巻く状況や社会経済情勢の変化に的確に対応し、その運営改善等の見直しに積極的に取り組むことが求められている。
平成17年12月定例会において第三セクター等に関する特定事件の調査を行うため「第三セクター等調査特別委員会」(以下、特別委員会という。)を設置し、この度のクラシック島根開発㈱の民事再生法の手続きにより、第三セクターの意義を改めて見捉えて公益性判断による市の関与と市財政状況が一段と悪化する中での公的支援のあり方、指定管理者制度の導入に際し、業務委託等これまでの経過を検証するとともに今後のあり方について調査研究を行うこととした。
検討課題
クラシック島根開発(株)に関する第三セクターとしての扱いと今後の対応
具体的調査事項
- (1)第三セクターとしてのこれまでの市の関与と支援状況の把握の検証
- (2)今後の公的支援のあり方
区分(中期)
検討課題
第三セクター等の個別的事業の経営上の課題と見直し
具体的調査事項
パークゴルフ場事業及び(財)三刀屋農業振興センター等の取り扱い
区分(長期)
検討課題
三セクター等の経営に関する市の関与と指導監督のあり方と国の指針に基づく検証
具体的調査事項
- (1)市民バス運行事業の業務委託の導入等のあり方
- (2)第三セクター等の見直しと指定管理者制度の導入による活用と管理のあり方
短期については、平成18年3月定例会に中間報告を行った。中期、長期については、遅くとも平成18年9月定例会を目途に最終報告を行うこととした。
- 第2 短期課題に対する調査報告
- 1.当面の課題に対する中間報告(文末添付)
平成18年3月定例会において、当面する課題に対する扱いと今後の対応についての中間報告を行った。
その要点は次のとおりである。 - (1)第三セクター等の市の関与・支援の検証
- (1)第三セクター等の支援の基本的考え方
- (ア)第三セクターとしての市の支援のあり方
- (イ)第三セクターへの補助金交付のあり方
- (ウ)議会への説明責任と市民への情報公開
- (2)第三セクターに関する指針における検証
- (ア)クラシック島根開発(株)に対する市の支援について
- (イ)クラシック島根開発(株)に対する市の関与について
- (ウ)今後の市としての公的支援のあり方について
- (3)今後の支援策に対する補助金交付としての検証
- (ア)補助金の交付のあり方
- (イ)補助金交付のチェックポイント
- (4)クラシック島根カントリークラブへの今後の支援策等について
- (ア)今後の支援を行う場合の市と経営者側とのゴルフ場経営に関する基本協約の締結を行うこと
- (イ)市としての支援策のあり方についての提言
- (2)中間報告後の動向
クラシック島根カントリークラブは、裁判所から民事再生法の許可により、新会社への営業譲渡の手続きとリニューアルのためのゴルフ場整備が行われ、5月に仮オープン、6月1日から正式にオープンし、現在に至っている。
第三セクターのクラシック島根開発(株)は営業譲渡と会社の精算手続きを行い、今年中にはすべての手続きが完了することになる。市としては破綻に伴う債務負担はないものの、精算により出資金は消滅する。 - 第3 中期・長期課題に対する調査報告
- 1.第三セクター等の個別的経営上の課題と今後のあり方
- (1)パークゴルフ場事業(明石緑が丘公園)
- (1)現状と課題
明石緑が丘公園は、平成12年1月に設立し、施設の管理運営について第三セクターの(株)みとやが運営を行っている。管理運営する施設はパークゴルフ場をはじめ、スポーツ施設(サッカー、野球、テニス)コテージ、ふれあい館などである。
当初、事業としては、住民の健康増進や福祉の向上、憩い、保養の場の提供、地域間交流の促進等地域の活性化等の役割を担った施設として事業展開が期待された。
しかしながら、類似するスポーツ、レクリエーション施設が複数立地しており年々利用者が減少しており、業務の効率化と営業力の強化が望まれている。
合併後についても管理委託において、指定管理者として当面3年間の指定を行ったが、特に当事業のメイン施設であるパークゴルフ場の取扱いについて、事業収益の減少から経営自体のあり方が課題となった。
昨年11月末、パークゴルフ場を廃止してバラ園に用途転換をするとの報道が一部新聞に掲載され、各方面から市の取り組みに対して不信や不満の声が出された。
平成18年3月24日には明石緑が丘公園パークゴルフ場廃止、用途変更に反対する会(代表者 早川正三)より3,006名の反対署名を添え要望書が市長、議長あてに提出された。
その後反対する会、(株)みとや等それぞれ協議が行われる一方、バラ園を経営する(有)フレグランス・ロゼとの協議も行われており、双方が一定のところで、納得できるかの調整協議が現在も行われている。 - (2)今後のあり方についての具体的取り組み
- (ア)魅力的な施設づくりと地域住民との連携
スポーツ、レクリエーション施設として社会的便益が広く地域にもたらす効果を最大限に活用するため、住民の健康増進や福祉の向上など魅力的な施設づくりの再構築が望まれる。
また、当施設の建設については、三刀屋町を中心に地域住民が一体となり長い時間の英知を結集し、作り上げた経過がある。
施設運営においては地域住民等との連携や協力が不可欠であり、住民と行政の協働による地域づくりを推進し、真に住民が主役のまちづくりに取り組むことが重要である。 - (イ)経営改善と営業努力
指定管理者としての管理委託を受けた(株)みとやとしては第三セクターとしての設立当初の意義を再確認し、施設存続の強い要望に応えるためにこれまで以上の経営改善と営業努力に努めることが望まれる。
しかしながら、経営上の問題として財政負担にも限界があり施設としての活用推進を図っていかなければならないが、市の責任として経営に対する監督・指導の充実強化し、地域住民の理解を得て経営の点検を行い、更なる経営健全化に積極的に取り組むことが重要である。
そこで事業内容、経営状況、公的支援等について改善を図りながら、施設の存続を前提にし、用途転換も視野に入れた見直しも検討課題といえる。その際、適宜適切な議会等への状況説明を行うとともに、住民に対する積極的かつわかりやすい情報公開に努めるべきである。
今後は、当初の目的を損なうことなく、施設の活用が出来る方策を地域住民と一体となって探っていくことが重要である。 - (2)掛合農村開発株式会社
掛合農村開発(株)は昭和63年4月に日本の道の駅発祥の掛合の里(地域特産品流通販売促進施設(レスト&ショップ)、地域特産品流通販売促進施設(農産物直売所)、交流の館、緑地公園)の3施設を管理運営する第三セクターとして誕生し、18年余りが経過している。近年経営状況は下降線をたどり、単年度決算でも赤字が発生し、出資金を減資し、その補填を行っていたが、将来的な第三セクターでの経営の見通しなどを検討し、第三セクターを解散し今後は民間のノウハウや営業戦略を積極的に取り入れるため、レスト&ショップと農産物直売所は指定管理者制度に移行し、平成18年9月より指定することとなる。なお、緑地公園については当面市の直営で管理することとなる。
8月30日には臨時株主総会で解散議決がなされ、これを受け年内を目途に清算が行われる。清算にあたっては赤字補填が減資等により処理されているが、関係法令により適切な処理がなされなければならない。
また、今後の指定管理者制度による管理運営にあたっては、市としての責任を果たし得るよう適切に指導・管理を行うことができるような措置を講じるべきである。 - (3)財団法人三刀屋農業振興センター
(財)三刀屋農業振興センターは、三刀屋町総合営農拠点施設として当時の三刀屋町が100%出資の財団法人として、平成10年11月に設立され花の栽培指導や生産振興を行ってきた。しかしながら、合併時の公益法人の取扱いについて協議調整を行い、市において、その役割や実態を踏まえ、整理・統合を検討し、財団法人に対して解散申し入れを行った。財団法人の理事会において協議され、平成18年3月末に一定の条件を付し、解散することについて承認された。解散にあたっては財団法人の業務・職員・財産等が関係法令及び市と財団法人との解散に係る協議事項を踏まえ、適切に処理されることが必要である。 - 2.市民バス運行事業の現状と課題に対する検証
- (1)市民バス運行事業の現状と課題
市民バス事業は旧6町村の運行形態を引き継ぎ、掛合町のだんだんタクシーを含め計25路線で運行されているが、運行便数や運行日等のサービス水準に地域間格差が生じている。また、専用スクールバスについても旧町村の運行形態を引き継ぎ5町で11路線が運行されている。
市民バス事業は平成17年度に一定の見直しを図り、18年度よりダイヤ見直しを図り運行されている。次に運行業務については、市民バスは25路線を第三セクター2社、民間5社の計7業者に対し、委託されている。またスクールバスは、吉田町の直営を除き民間の4社に対し委託している。運行管理の統一、委託料の削減など財政効果を図るために市民バス事業の委託業務の一元化を図るとの方針が示されたが、住民サービスや安全な運行管理の面など検討課題が多く、平成18年度は見送られ、従来の運行管理業務委託となっている。(別表1参照) - (2)市民バスとJR木次線の競合及び接続についての現状と課題
JR木次線は通勤、通学はもとより、松江方面への交通手段として利用されているが、乗車人数は年々減少の一途をたどっている。特に平成14年度以降の木次線における雲南市域の乗車人数は減少している。
このことは市民バスとJR木次線の競合や接続が十分ではない点などが指摘されている。一方、これまで行ってきたJR木次線の存続運動は、広域の市町で利用促進の取り組みとしてトロッコ列車の活用や、乗車向上に向けた取り組みを展開し、JRと関係市町で連携・協力を図ってきた。
現在運行にあたってはJRとの協議が行われているが、双方が連携して、住民サービス向上対策と乗車向上対策に取り組む必要性に迫られている。
市としては広域バスをはじめとするJRとの接続について再検討し、双方の努力により出来る限り競合を避け、引き続きJR木次線の存続を関係団体と連携をとり、取り組むことが望まれる。 - (3)市民バス事業の見直しによる業務委託のあり方
- (1)市民バス事業の効率的な運行における検討課題
- (ア)住民サービスの向上
- (イ)効率的な運行管理
・運行便数、時間等について随時チェックを行い定期的な見直し
・乗車数の把握を行い、一定基準を定め、より効率的な運行
・市民バスとスクールバスの一体的な利用 - (ウ)JR木次線存続に向けた取り組みの強化
- (2)バス運行業務における業務委託のあり方
バス事業の運行委託は道路運送法等の諸規定により行うことになる。現在市民バスの業務委託については第三セクター2社、民間業者5社の計7社に委託している。平成18年度における業務委託の方針として運行管理の統一、委託料の削減等の財政効果を図るため業務委託の一元化が提案されたが、現状と課題が整理できず1年間現状で行うこととなった。
そこで地域の実情を考慮し、サービスの低下につながらないように一定の基準を定め、効率的な運行管理を行うために現行の業務委託のあり方を見直し、一元化ではなく地域バスの特性を活かし、適切な運行管理を行うべきである。
高齢化社会及び子供の安全確保の観点から、市民バスの役割は重要性を増している。
今後、業務委託についてはただ単に経費の削減を図るだけではなく、住民へのサービス、安全性の確保、地域振興等を図るために価格その他の条件を総合的に評価する制度など検討すべきである。 - 3.地方行政改革指針(平成17年3月29日総行整第11号)に基づく第三セクター等に関する検証
- (1)第三セクター及び財団法人の見直しの状況
雲南市が出資する第三セクター及び財団法人の概要は別表2のとおりである。
合併後雲南市第三セクター事業等マネジメントの基本指針が平成17年度に策定され、指定管理者制度の導入により一部が見直しされたが、設立経緯、雇用及び事業継続性の確保などの理由から非公募原則3年の指定期間として、従来の受託者を指定管理者として指定した。
第三セクター、財団法人の見直し状況は別表3のとおりである。具体的な見直し方針は、管理運営を指定管理に移行する。
見直しにあたっては次の事項に要約される。 - (1)行政補完型の地域振興事業の管理運営は原則として従来の受託者を指定管理者として指定する。
- (2)行政補完型の文化事業の管理運営はできる限り一元化する方向で指定管理者の指定について一部見直しを行う。
- (3)バス事業に関しては業務委託として運行形態や地域的状況を踏まえ効率的な運行管理を行う。
- (4)事業内容を精査し、法人の解散及び事業内容の見直しを行い廃止又は用途変更を行う。今後も経営状況をチェックし、適切な判断が必要である。
そのうち(3)については別途バス事業の項目で詳細に検証を行う。また(4)についても前記4の個別的事業で詳細について記載を行っているので参照されたい。
- (2)出資比率の現状と見直しにおける考え方
雲南市が出資する第三セクター及び公益法人の出資比率は別表4のとおりである。
合併後の見直し前と比べ現時点では変更がない。第三セクター等マネジメント基本方針によると市の強い関与が必要な文化事業の推進を使命とする「(株)遊学」及び「(財)鉄の歴史村地域振興事業団」については、出資比率50%以上を確保することとし、他の第三セクター等については3分の1程度の出資比率となるよう努めることとしている。 - (3)第三セクター等の出資比率の検証における論点とあり方
第三セクター等に出資・出捐を行っている自治体はその経営状況の点検評価を定期的に行うことが必要である。
この点検評価は経営指標の分析などによる経営の健全度の診断、事業計画と実績との対比に加えて、設立目的、主旨に沿って事業が展開されているか、事業内容の見直しが必要ないかといった観点からも行う必要がある。
そこで、第三セクター等の運営に対して、その出資比率に応じて、自治法及び商法上の制度又は株主としての権限として、関与することができ、これらの制度を十分に活用する必要がある。出資比率は一般的には必要最小限とすることが適当であるが、自治法上の制度として出資比率が4分の1以上の法人に対しては、監査委員による監査が行える。
出資比率を検討する際には、すべての第三セクター等に対して公平・公正を期した上で市の関与の必要性から、その権限を十分に考慮した対応が必要である。 - (4)「公の施設」の指定管理者制度導入の推移
平成15年9月の指定管理者制度の創設に係る地方自治法の改正前の管理委託制度により出資法人、公共団体または公共的団体へ管理委託している公の施設については、平成18年9月からの指定管理者制度への移行期限までに当該出資法人を指定管理者に指定するか、新たに民間事業者等を指定管理者に指定するか、また当該施設を廃止するか等管理あり方について検証を行った。その結果、平成18年7月末の公の施設の管理状況は別表5のとおり、指定管理者制度へ移行した。 - (5)指定管理者制度の活用と管理のあり方についての検証
国が示した地方行政改革指針に示された民間委託等の推進については、強く民間解放を促す内容となっており、指定管理者制度の活用としては次のとおりである。 - (1)すべての公の施設において管理のあり方について検証を行い、検証結果を公表する。
- (2)平成18年9月の指定管理者制度への移行期限までに当該出資法人等を指定管理者に指定するか、しないか、または廃止するか等、管理のあり方について検証する。
- (3)管理のあり方の検証に際しては、行政としての関与の必要性、存続か廃止かなど、その比較等も含め、決定理由を明らかにした上で住民等に対する説明責任を十分に果たす。
- (4)公の施設の管理状況については、管理の主体や管理の状況など具体的内容を公表する。
雲南市では指定管理者制度の指定については現行施設の移行は平成18年9月までの期限に一部を除きほぼ完了している。 - 第4 おわりに
- 1.調査研究の審査経過
平成17年12月定例会の最終日に特別委員会を設置。以来8ヵ月間に13回の特別委員会を開催し、平成18年3月定例会に中間報告を提出し、この度最終報告を行うこととなった。
その間、第三セクター等に関しては、合併時には出資する第三セクター及び公益法人の経営診断調査が行われ、合併後の雲南市としての第三セクター事業等マネジメントの基本方針の策定など、その取扱いが協議されてきた。
当委員会の調査研究は、雲南市の指針をはじめ、総務省が策定した第三セクターに関する指針(平成15年12月改定分)並びに地方行政改革指針(平成17年3月策定)に基づき、第三セクター等のあり方について地方財政との関わりにおいて審査を行った。 - 2.報告の要点
この報告において、第三セクター等に関する審査については、基本的事項として次の3点に要約した。 - (1)第三セクター等のあり方と抜本的見直しの方策
次の事項に留意し更なる経営改善に積極的に取り組むこと。 - (1)行政評価の視点を踏まえた点検評価の充実・強化と自治法上、商法上の権限の有効活用を図ること。
- (2)事業内容、経営状況、公的支援等について、適宜適切な議会への状況説明を行うとともに、住民に対する積極的かつ分かりやすい情報公開に努めること。
- (3)統廃合、民間譲渡、完全民営化を含めた既存法人の見直しを進めること。
- (4)経営状況が深刻であると判断される場合には、問題を先送りすることなく、経営悪化の原因を検証し債権者等関係者とも十分協議しつつ抜本的な経営改善策の検討を行うこと。その上で経営の改善が極めて困難と判断されるものについては法的整理の実施等について検討すること。
- (2)財政負担のあり方と住民サービスの向上と業務の効率化
次の事項に留意し、市の支援と関与における財政負担等のあり方と住民サービスの向上と業務の効率化を図ることとする。 - (1)前記(1)において、経営改善の方策に関し、特に財政負担のあり方について具体的経営指標を定め、監督・指導体制を強化し、必要最小限の負担とすること。
- (2)第三セクター等への補助については、常に自治法上の公益性判断を検証し、交付すること。
- (3)バス事業の業務委託については、委託料の縮減など財政効果を図ることはもとより、サービスの低下にならない利便性と運行上の安全性などを十分に考慮し、実施すること。
- (4)指定管理者制度の活用にあたっては管理のあり方を検証し、効率的にサービスを提供できるかの判断により実施すること。
尚、国において夕張市の事例などから第三セクター等の負債など地方債残高を示す新たな指標などの自治体の再建・整備が検討されており、今後行財政の再建に向けての改善を図るための検討が求められている。 - (3)魅力ある施設づくりのための地域協働と情報公開
魅力ある施設づくりには、地域住民等との連携や協力が不可欠であり、次の事項に留意し、地域と一体となった取組みが必要である。 - (1)第三セクター等の設立の経緯と意義を踏まえ、経営状況の見通しなど方向性を定め、地域住民の理解と協力のもと、適切な対応に努めること。
- (2)合併により、地域の拡大に伴う広域的な見地から旧町村の垣根を取り除き地域間の交流の促進、地域の活性化等を積極的に展開すること。
- (3)生活に密着した事業は少子高齢化や地域の課題、ニーズに対応しなければならない。そのためには住民参加や地域自主組織等の理解により地域協働の積極的な連携・協力を図ること。
- (4)地域住民に対しては、より分かりやすい形で積極的にホームページや広報等を通じて情報提供を行うとともに住民の意見を反映するなど十分な理解を得るよう努めること。
- 3.今後の検討課題
今回の第三セクター等調査特別委員会の調査・研究は、第三セクターであるクラシック島根カントリークラブの民事再生法の申請を発端に設置し、合併後の第三セクター等に関する現状と課題を検証し、国が示した第三セクターに関する指針に基づき今後のあり方について提言した。
雲南市は平成16年11月1日の6町村合併から、まもなく2年を迎えようとしている。
この間、国においては平成18年度までの第一期の三位一体の改革に一定の目途をつけ、新たに平成19年度からの第二期の改革の実行に向け地方六団体等の関係機関の協議が行われているが、これまでの地方切捨ての施策ではなく、地域の実態に即した住民本位の取り組みが必要である。
新三位一体の改革では、夕張市の事例などから自治体の再建法制の整備を視野に入れた取り組みが行われようとしており、自治体のより責任ある財政運営が迫られている。
当面する行政課題は、雲南市は厳しい財政や状況の中で行財政改革の取り組みを行っているが、一方合併後の事務・事業の一元化や地域の協働・連携など広域化した自治体としての整備が喫緊の課題である。
このような状況の中、雲南市として市民の視点に立ち、不断の行財政改革に取り組むために住民と協働し、首長のより責任あるリーダーシップの下、危機意識と改革意欲を共有し取り組んでいくことが重要である。
また、議会においても行財政改革の推進のために、その機能を十分に発揮し、住民福祉の向上を目指し、住民の付託に応えなければならない。
終わりに今回の報告は、雲南市議会として特定事件に関する調査・研究の最初に取り組んだものであり、今後、雲南市の将来を見据えて自らどのように変わっていくべきかを考えながら、『雲南市に住んで良かったと思えるような豊かな自治と新しい雲南市に』を市民総ぐるみで議論していきたい。
 お問い合わせ先
お問い合わせ先
- 議会事務局 総務課
- 〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1 - Tel 0854-40-1004
- Fax 0854-40-1009
- gikai@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。

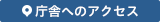

 妊娠・出産
妊娠・出産 子育て
子育て 学校・教育
学校・教育 結婚・離婚
結婚・離婚 住まい・引越し
住まい・引越し 就職・退職
就職・退職 高齢者・介護
高齢者・介護 お悔やみ
お悔やみ

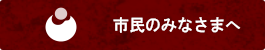
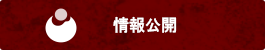

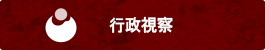
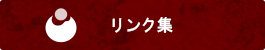
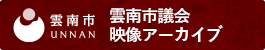


 利用者別メニューから探す
利用者別メニューから探す


 お問い合わせはこちら
お問い合わせはこちら