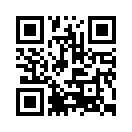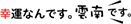市長コラム市報うんなんに掲載しているコラムをご覧いただけます
 市長コラム
市長コラム
市長のコラム
毎月発刊の「市報うんなん」に掲載しているコラムをご覧いただけます。
令和7年12月
この一年を振り返り
令和7年もあと少しとなりました。今年は、大きな災害こそありませんでしたが、夏の酷暑と水不足、物価の上昇により、ご苦労された方も多かったものと思います。そうした中でも、お仕事に、地域活動に、学業に、子育てに、様々な分野で頑張ってこられた全ての皆様に心から敬意を表します。
国際情勢や気候変動を背景に世の中が激しく変化し、先行きが見通せない中でも、変化への対応を余儀なくされた1年でありました。
しかし、変わらぬ暮らしと地域の絆、未来への希望の大切さを改めて感じ、「未来のためにあきらめない」という思いを強くしたところです。
今年も、そしていつまでも、穏やかな年越しをお迎えいただけますようにお祈りいたします。
令和7年11月
農業について考える
勤労感謝の日は、かつては新嘗祭といって今年の収穫に感謝する祭日でした。
今年は、水不足や猛暑により農家の皆さんは大変なご苦労をされたことと思います。そうした中でも地域によって差はあるものの、嬉しい収穫を迎えられたと感じております。
昨年来の米価の高騰は、農家にとっては喜ばしい反面、消費者にとっては物価の高騰と相まって家計に厳しい側面もあります。将来的に程よい価格、安定した価格が維持されることを期待しています。
米の増産と輸出推進の農政への転換が図られつつありますが、これは輸出用の低価格の米が増えることも意味しています。
雲南市の様な中山間地域では、コスト勝負では不利な地域が多く、高い品質とブランド力による「高値でも売れるコメ」づくりが一層重要になってくるものと考えております。
美味しい新米をいただきながら、これからも持続していく農業の在り方を、皆様とともに考えてまいりたいと思う秋の日であります。
令和7年10月
スポーツのまちづくりを考える
今夏は、全国高校総体レスリング競技大会が雲南市で開催されました。ひたむきに勝利を目指す若者の姿は感動を生み出しました。
令和12年の国民スポーツ大会では、レスリング、ソフトボール(少年男女)、ローイングが雲南市で開催されます。地元高校の部会同のほか、このたび本拠地を愛知県から雲南市に移す女子ソフトボールチームの活躍も期待されます。
スポーツは競技として、勝利を目指すのは当然ですし、応援する選手が活躍すれば嬉しいものです。
しかし、スポーツの言葉の起源が「楽しむ」であるように、勝敗を一つの過程としながら、試合やそこに至るまでの努力、一緒になって心を躍らせること全てを「楽しみ」として、生活を張りのある生き生きとしたものとしていくことこそ大切にすべきものだと思います。
国民スポーツ大会を契機として、国スポ競技以外の種目も含め、スポーツを「楽しみ」と捉えて生きがいと健康づくりに生かしていく文化、いわゆる「スポーツ文化」が育つことを期待しています。
令和7年9月
少子化を考える
令和6年の日本の出生数は69万人弱となり、昭和48年の209万人をピークに減少が続いています。経済の発展とともに都市化と少子化が進むのは世界に共通する傾向です。裕福になればこどもが増えると思えるのですが、なぜでしょう。
結婚した夫婦が生む子どもの数は、昭和47年が2.2人、令和3年が1.90とそれほど変わっていませんが、結婚したカップルの数は昭和47年は110万組だったものが令和5年には48万組と半減し、50歳時未婚率も大きく上昇しています。結婚しない人が増えたこと、これが少子化の最大の要因です。
その大きな要因は昔に比べ「楽しいこと」が増えるとともに、「子育ての大変さ」が強調される風潮の中で、「家庭を持つことの楽しさ」が認知されにくくなっていることに大きな要因があると感じています。
家庭を築き持続することは確かに労は多いかもしれませんが、それをはるかに上回る喜びがあることを、若い世代の方々に伝えていきたいと思っています。
令和7年8月
戦後80年を迎えて
先の大戦から80年。その間私たちは平和の利益を享受してきました。私も戦争を知らない世代ではありますが、戦中戦後を通じて平和な「今」の礎を築いていただいた多くの英霊や先達の方々に、心からの感謝を申し上げます。
最近、さまざまな違いをもとに、対立を助長する風潮が強いように感じます。対立の先に何か恐ろしいものがあるように感じるのは私だけでしょうか。
互いの共通点を見つけ、違いを認め合い、歩み寄る工夫を互いに行っていくことが、平和を維持するために大切な思考プロセスです。
その取り組みは、Iターン者や外国人など様々な人との「共生」を目指す「えすこな雲南市」に通ずることでもあります。
「愛語よく廻天の力あり」とも申します。思いやりの気持ちで住みよい雲南市にしてまいりましょう。
令和7年7月
二地域居住のこれから
仕事や家庭の都合で転居はしたものの、定期的に元の家に戻って田畑の管理や近所の会合にも参加する方が増えてきているように感じます。
また、都会に居住しながらも仕事や様々なご縁を得て、雲南市と都会を行き来しながら暮らす人もいらっしゃいます。吉田町宇山の草刈り応援隊、大東町山王寺のオーナー・トラスト制度など、市外・地域外の力を生かす取り組みも進んできています。
人口は国勢調査や住民票の登録者数を基礎に計算されますが、実際には、数に現れない市外の方々もさまざまな形でまちづくりに参加されているわけです。
人口が減少する中では、こうした「関係人口」を増やすことで地域の行事や環境を維持し、活性化につなげていくことが今後ますます大切になっていきます。
国においては「ふるさと住民登録制度」の創設を検討されており、その成立に大きな期待をしています。
それぞれの地域の魅力を生かしながら、地域外の人々とも共に生きる「えすこな雲南市」を目指していきましょう。
令和7年6月
雲南市の食文化を繋ぐ
お茶口に「煮しめ」が出てくるのは出雲地方の文化だと思います。季節の旬のタケノコやフキ、手作りのこんにゃくなどが、色鮮やかに美味しく炊かれているのを見て、口にするにつけ、すごい技術だと感心するばかりです。
昔から、ご近所の人が集まってお茶を飲みつつ、それぞれの家庭の味を密かに競い合った結果、文化にまで昇華したのではないかと思うところです。
こうした文化を次の世代に繋いでいくには、それを守ってきた「世代間の繋がり」を大切にしていくことが必要ですが、学びあいの場を作るなど皆さんとともに工夫をしてまいりましょう。

令和7年5月
「えすこな 雲南市」の実現に向けて
職員からの提案で、私の言葉をお伝えするコーナーができました。文才無き身ではありますが、ご覧いただけると幸甚に存じます。
初回は、やはり総合計画のめざす姿「えすこな 雲南市」です。方言はその地域の文化や精神性を色濃く反映します。市民の皆さんとの議論を通じて「えすこ」に含まれるニュアンスこそ、雲南市で暮らす人々の共通の価値観だと再認識しました。対立ではなく協力、利己でなく利他の精神を基盤として、調和の中で持続可能な雲南市を皆さんとともに一緒につくってまいりましょう。

 お問い合わせ先
お問い合わせ先
- 総務部 秘書室
- 〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1 - Tel 0854-40-1021
- Fax 0854-40-1029
- hisho@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。

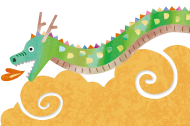

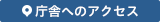

 妊娠・出産
妊娠・出産 子育て
子育て 学校・教育
学校・教育 結婚・離婚
結婚・離婚 住まい・引越し
住まい・引越し 就職・退職
就職・退職 高齢者・介護
高齢者・介護 お悔やみ
お悔やみ

 利用者別メニューから探す
利用者別メニューから探す







 お問い合わせはこちら
お問い合わせはこちら