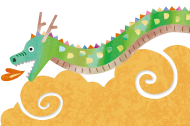さくら色々 Vol.8
|
| このコーナーでは、さくらに関する知識や「さくら守」として年間を通して手入れをする中で、経験したことを紹介します。 |
| |
 |
| さくら守 遠田博 さん |
手強い質問パート2
先月号に続き、小学校で行うさくらの授業の際に受けたさくらに関する質問の内、なるほどと言う質問とその答えを紹介します。
質問1
なぜ、さくらは春に咲くのですか
答え
なぜ春に咲くのかは、「さくらに聞いてみないと分からない」が本音ですが、ただ、春に咲くさくらの代表品種ソメイヨシノが咲く仕組みは分かっていますので、紹介します。
ソメイヨシノの花芽は、前年の9月までにはできあがっています。そして、この花芽には葉でつくられた休眠物質が送られ、10月上旬には冬の眠り「冬休眠」に入っています。
もしこの時期に台風や毛虫によって葉が無くなると、休眠物質がつくられなくて、秋に開花(狂い咲き)することがあります。
冬休眠状態の花芽は、冬になって最低気温が10℃を下回ると、それが刺激となって冬休眠から徐々に覚め、2月に入り気温が少しずつ上昇し始めると、花芽の発育が始まり、その後は暖かいほど開花が早くなります。したがって、この地方でも冬の気温の違いによって、早い年は3月20日頃、遅い年は4月5日頃と開花日に差が出ます。
質問2
なぜ、枝垂れ桜の枝は枝垂れるのですか
答え
普通、さくらの枝は上の方へ向かって伸びますが、枝垂れるようになったのは、野生種のさくらの突然変異によって、枝が下の方向に伸びるようになったためです。
それではなぜ枝が下の方向へ伸びるのかですが、それには植物ホルモンの「ジベレリン」の量が影響していて、枝垂れ桜は枝が成長する過程で、縦方向へは良く伸びますが、横方向(太る)へはジベレリンの供給不足により枝が太らないため、細長い枝ができ、自分の重さを支えることができず、枝が垂れるようになったためです。
以上、前回と今回で三つの手強い質問を紹介しましたが、次に小学生から何が出てくるか楽しみです。 |

加茂町 段部の枝垂れ桜
品種名:シダレザクラ
エドヒガンの突然変異 |
| |
| |
| |
|