| 総務課 0854-40-1027 |
| |
| 今年も6月9日ごろの中国地方の梅雨入りが報じられました。大雨による風水害や土砂災害に注意が必要です。梅雨と言えば6月を想像しますが、近年6月よりも7月の降水量が多い年が目立ちます。各地で集中豪雨による災害が多発しており、局地的に大雨が降る「ゲリラ豪雨」の報道も耳にします。平成18年7月豪雨も記憶に新しいところです。日ごろから家庭や地域で防災用品を準備したり、避難場所の確認を行ったりして、いざというときに備えましょう。 |
| |
防災訓練
|
| 5月30日、斐伊川河川敷での第15回斐伊川水防演習に参加した国、県、斐伊川沿岸自治体の防災担当職員や水防団員らが水防工法の訓練などを行いました。 |
| |
 |
 |
 |
| 地元の斐伊地域防災会議も初参加 |
月の輪工を行う水防団員 |
伝統の出雲結い工 |
|
| |
| 6月7日、木次町の三新塔地区で土砂災害を想定した避難訓練と研修会が行われ、地区住民が真剣に訓練に取り組みました。 |
 |
 |
 |
| 避難所へ向かう参加者 |
避難者の確認 |
雲南消防本部による河川救助訓練 |
|
| |
こんな現象を見たら、聞いたらすぐに避難!
|
| ・山鳴りがする |
・地面が振動する |
・雨が降っているのに川の水位が下がる |
| ・川が異常に濁る |
・流木が発生する |
・小石がバラバラ落下する |
| ・小崩落が発生する |
・斜面から水がふき出す |
・湧き水が濁る |
| ・普段、きれいな井戸水が濁る |
・斜面に亀裂や段差、ふくらみが発生する |
|
|
| |
| |
自主防災組織の重要性
|
平成7年1月17日の阪神淡路大震災の教訓
地震発生直後、各消防署に通報や駆け込みが殺到。火災現場では断水で消化に必要な水の確保ができない、要員や資機材が追いつかず、倒壊した建物で道路が寸断され現場に急行できないなどの事態が起こりました。阪神・淡路大震災のような災害が発生した場合、普段のように消防車や救急車が駆けつけることは困難です。
こうした中、大きな力を発揮したのは近隣の人たち。生き埋めや建物等に閉じ込められた被災者のうち、消防などの専門の救助隊から助けられたのは、全体のわずか1.7%。90%の人が、自力または家族、近隣の人々によって救助されました。 |
| |
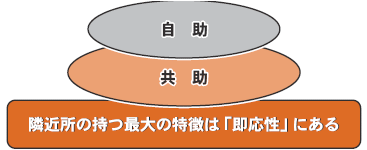 |
| |
ハザードマップ
|
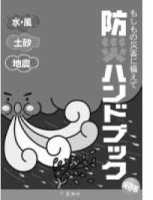 今年4月の自治会発送で市内の全世帯へ「防災ハンドブック(防災ハザードマップ)」をお配りしました。 今年4月の自治会発送で市内の全世帯へ「防災ハンドブック(防災ハザードマップ)」をお配りしました。
ハザードマップ(災害避難地図)とは、大雨により河川が増水・氾濫した場合に想定される浸水の範囲(浸水想定区域)とその深さ、ならびに土砂災害が発生するおそれのある区域や各地区の避難場所を示し、市民のみなさまの安全な避難に役立つように作成した地図です。いざというときに備えて、自宅から避難場所までの経路や家族の連絡先などを書き込んで、見やすい場所に保管しておきましょう。 |
| |
平時の備え
|
(1)家屋の安全確認、補強
地震:家や塀の耐震化、家具類の転倒・落下の防止等
風水害:屋根、看板、雨どい、側溝、樹木等の点検
(2)防災用品の準備
ラジオ、懐中電灯、シート、かなづち、ロープ、医薬品等
(3)非常用飲料水、食糧の準備
1人1日分の水と食糧(インスタント食品、缶づめ、ミネラルウォーターなど)
(4)生活必需品の準備
下着、毛布、タオル、石鹸、ちり紙、マッチ等
(5)家族で防災会議
地震発生時のためにそれぞれの役割を決めておく
(6)避難所の確認
近所にある避難場所、避難経路等を確認
(7)防災講習会、訓練へ参加
地区・地域で行う訓練等に参加
(8)消火器、消火用水の準備
風呂の水をためておく
(9)自主防災組織への参加 |
| |

