項 目
(1) 県消消防操法大会「三刀屋方面隊が準優勝」
(2) 議員報酬引き上げの答申
(3) 雲南市まちづくり条例の制定に向け
(4) 新成人が新たな誓い
(5) 国有林と民有林が連携
(6) リッチモンドサマースクール
(7) 子どもたちを犯罪から守ろう |
| |
|
| (1) 県消消防操法大会「三刀屋方面隊が準優勝」 |
| |
 |
| |
 8月3日、出雲ドームで第52回島根県消防操法大会が開催され、雲南市からはポンプ車の部に三刀屋方面隊、小型ポンプの部に大東、加茂の方面隊が出場しました。 8月3日、出雲ドームで第52回島根県消防操法大会が開催され、雲南市からはポンプ車の部に三刀屋方面隊、小型ポンプの部に大東、加茂の方面隊が出場しました。
このうち、三刀屋方面隊は大舞台の重圧に負けることなく、素晴らしい演技を披露。機械操作、ホース延長、放水などの動作を確実に行い、見事準優勝に輝きました。
大東、加茂の両方面隊も入賞こそ逃したものの、春先から連日取り組んだ練習の成果を十分に発揮。きびきびとした動きで、正確な操法を行いました。
 また、前日の2日に行われた第60回島根県消防大会では、かもめ保育園幼年消防クラブが県知事表彰をうけました。同クラブの年間15回に及ぶ避難訓練の実施など防火活動が高く評価されたものです。 また、前日の2日に行われた第60回島根県消防大会では、かもめ保育園幼年消防クラブが県知事表彰をうけました。同クラブの年間15回に及ぶ避難訓練の実施など防火活動が高く評価されたものです。 |
| |
|
| (2) 議員報酬引き上げの答申 |
| |
 |
| |
7月17日、雲南市特別職報酬等審議会から速水市長に対し、議員報酬の引き上げなどをまとめた答申が行われました(表のとおり)。
議員報酬については、県内他市及び全国類似団体と比較して低位であること、議員定数が24人に削減されることなどから総合的に判断。松江市、出雲市と雲南市を除く県内5市の平均報酬額が妥当とし、引き上げることとされました。
市長、副市長、教育長の給料額については、現在、給料減額期間中であり、改訂した場合に減額率にも影響を及ぼすことから、改定は見送られました。
市では、この答申を受けて条例改正案を9月議会に提案する予定です。 |
| |
| ◆報酬額、給料額比較表 |
| 区分 |
現行 |
答申 |
比較 |
| 報酬月額 |
議長 |
376,000円 |
413,000円 |
37,000円 |
| 副議長 |
327,000円 |
354,000円 |
27,000円 |
| 議員 |
306,000円 |
328,000円 |
22,000円 |
| 期末手当 |
加算率 |
10% |
15% |
5% |
| 支給率 |
3.35月 |
変更なし |
― |
| 給料月額 |
市長 |
890,000円(712,000円) |
変更なし |
― |
| 副市長 |
721,000円(612,850円) |
| 教育長 |
639,000円(555,930円) |
| 期末手当 |
加算率 |
15% |
| 支給率 |
3.35月 |
|
| |
|
| (3) 雲南市まちづくり条例の制定に向け |
| |
まちづくりの基本理念を明らかにするために制定する「雲南市まちづくり基本条例」のパブリックコメントを実施したところ、次のとおりご意見をお寄せいただきましたので、紹介します。
1.意見募集した条例:雲南市まちづくり基本条例(案)
2.意見募集期間:6月19日~7月18日
3.意見提出人数:1人(市民)
4.意見件数:2件
5.意見の概要と市の考え方(要旨) |
| 意見の概要 |
市の考え方 |
| 1 |
「新たな公共」という考え方が、果たして住民(市民)のためになるか。現実は、「福祉や環境」など本来は行政の責任でやるべきことが、個人ボランティアやNPO、町内会活動に「肩代わり」させられることが多くなっているように思う。 |
公共領域は、従来から行政のみならず、市民や民間セクターも担ってきていますが、公共サービスの担い手でもある市民が、その特性や長所を活かすことによって、住民ニーズにより対応した公共サービスの提供と社会的・地域的な課題の解決が図られるものと考えます。また、こうした「新たな公共」の考え方に基づいて、公共を担う多様な主体の役割や責務、それぞれの主体間の関係を明らかにしていくこと(過程など)が、市民が主役のまちづくりに重要であると考えております。 |
| 2 |
まちづくり基本条例に「市民が主役のまち(雲南市)」をつくることを明記し、情報の公開と提供を約束し、市民参加を進めるために、まず市が設置するあらゆる審議会や委員会には「男女半数」を基本に公募し、年齢構成が反映されたものにするべきである。 |
雲南市がめざすべきまちづくりの姿(理念)と基本となる考え方を示した前文で、「まちづくりの原点は、主役である市民が自らの責任により、主体的に関わることです。」と明記しております。 情報の公開と提供を約束するという点については、第7条(行政の役割と責務)で、「市民に利用しやすい形で保有する情報の積極的な公開・提供を行うとともに、常に分かりやすい説明を行なうこと」と明記しております。 審議会や委員会への市民参画については、第8条(附属機関等の委員への市民参画)で、「市長は、附属機関等の委員の選人については、幅広い人材を選出するよう努めなければなりません。」と明記しております。また、雲南市男女共同参画推進計画で審議会などの委員に占める女性の割合についての目指値も定めております。【参考:審議会等への女性の参画率 現状値(H18年度)26.4% → 目標値(H22年度)40.0%】 |
|
| パブリックコメントの結果は、市役所政策推進課または各総合センターでもご覧いただけます。 |
| |
|
| (4) 新成人が新たな誓い |
| |
 |
| |
アスパルで8月14日、平成20年度雲南市成人式が行われ、新成人549人(式典には388人が出席)が人生の節目に誓いを新たにしました。
式典では、速水市長が新成人を祝福し「様々な地域資源に恵まれた雲南市の魅力を発見し、市内で活躍中の人も、就職や進学で地元を離れている人も積極的にふるさとのまちづくりに参加してほしい」と、式辞を述べました。
 これを受け、京都で大学生活を送る白石祐介さんが新成人を代表してあいさつ。「雲南の豊かな自然や温もりのある人々の心など、『ふるさとの良さ』があらためてわかるとともに『ふるさとを誇りに思う気持ち』が心の底からあふれてきた」と自然も社会環境も異なる京都から見たふるさとへの思いを語り、「生まれ育ったふるさと雲南を守っていくのが私たちの使命だと思う。これまで支えてくださった多くの人への感謝を忘れず、ふるさとの誇りを胸に、これからの人生を力強く歩んでいく」と決意を述べました。 これを受け、京都で大学生活を送る白石祐介さんが新成人を代表してあいさつ。「雲南の豊かな自然や温もりのある人々の心など、『ふるさとの良さ』があらためてわかるとともに『ふるさとを誇りに思う気持ち』が心の底からあふれてきた」と自然も社会環境も異なる京都から見たふるさとへの思いを語り、「生まれ育ったふるさと雲南を守っていくのが私たちの使命だと思う。これまで支えてくださった多くの人への感謝を忘れず、ふるさとの誇りを胸に、これからの人生を力強く歩んでいく」と決意を述べました。
式典に続いて雲南市の魅力をたっぷりと詰め込んだ映画「うん、何?」を鑑賞。その後、町ごとに記念撮影をして、映画「うん、何?」に登場するヤマタノオチチ牛乳の味も楽しみました。
新成人らは、懐かしい友人との再会に、写真を撮ったり、思い出話に花を咲かせたりして晴れの門出を互いに祝いました。 |
| |
  |
| |
|
| (5) 国有林と民有林が連携 |
| |
 |
| |
森林共同施業団地を設定し、民有林と国有林が連携して森林整備を推進しようとする協定が7月29日、雲南市役所で国、県など施業団地の関係者により締結されました。
協定の対象となる区域は、掛合町の井原谷・南谷地内の森林443ha。このうち112haを協定期間内に整備する予定です。
事業地の集約化に努めることで、高性能林業機械等の導入が可能となり、効率的な森林施業と事業コストの削減を図ります。
近畿中国森林管理局島根森林管理署の長口深署長は、「森林の荒廃が進む中、民有林と国有林の連携は意義深い」とあいさつし、出席者らが林業振興の発展を願いました。 |
| |
|
| (6) 地域医療の拠点、雲南病院の支援策を考える |
| |
 |
| |
青少年の英語力向上や国際感覚豊かな人材の育成を目的に、夏休み期間中、中学生らをアメリカ・インディアナ州リッチモンド市に送る青少年海外視察等派遣事業。今年も、募集により選ばれた8人の中学生が同市を訪れ、ホストファミリーの元に滞在しながら、交流活動などを行いました。
 一行は、8月11日にリッチモンド市に向け出発。22日までの期間中、施設訪問や市内観光で見聞を広めました。 一行は、8月11日にリッチモンド市に向け出発。22日までの期間中、施設訪問や市内観光で見聞を広めました。
このうち、14日には、ホストファミリーら現地の人々に日本文化を紹介。ヤマタノオロチ、永井隆博士を題材に雲南の特色を英語で発表するなどしました。生徒らは「練習よりも上手にできた」とほっとした様子。リッチモンドの人々には書道が人気で、「平和を」と書いてもらうなど、交流を深めました。 |
| |
|
| (7) 雲南市クリーン大作戦 |
| |
 |
| |
雲南市の環境美化活動の重点活動日に設定された7月6日の早朝、大東町丸子山周辺と加茂町の赤川堤防及び河川敷で「雲南市クリーン大作戦」が行われ、集まった約300人の市民・事業者・市職員らが協同で、ゴミ拾いなどに汗を流しました。
この事業の目的は、空き缶のポイ捨てや粗大ゴミの不法投棄などが後を絶たない現状を認識し、子どもと大人が一緒になって美しく環境にやさしいまちをつくろうというものです。
同日午後からは、大東町女性の集いと雲南市の共催による「だいとうリサイクル推進大会」が大東町体育文化センターで行われ、約200人の参加者がビデオ上映や実践研修を通じてごみの減量化、リサイクル化など環境問題に対する理解を深めました。
今後、雲南市の環境をみんなで守る活動を全市に広げていきます。 |
| |
|
| (8) 子どもたちを犯罪から守ろう |
| |
 |
| |
各地で児童殺傷事件や通り魔事件が続発する中、犯罪を未然に防ごうと8月7日、アスパルで地域安全マップ研修会が行われ、雲南地区の防犯ボランティアや地域安全推進委員らが犯罪とその対策について学びました。
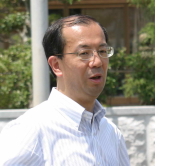 第1部は、立正大学の小宮信夫教授による基調講演。「犯罪は『この場所』で起こる」と題した講演の中で小宮教授は「犯罪が起こりやすいのは『入りやすく見えにくい場所』。その場所を見つけ、改善することで犯罪を防ぐことができる」と説明。安全マップ作成の必要性を訴えました。 第1部は、立正大学の小宮信夫教授による基調講演。「犯罪は『この場所』で起こる」と題した講演の中で小宮教授は「犯罪が起こりやすいのは『入りやすく見えにくい場所』。その場所を見つけ、改善することで犯罪を防ぐことができる」と説明。安全マップ作成の必要性を訴えました。
第2部は、フィールドワークと安全マップづくり。研修生が班ごとに三刀屋町内を歩いて回り、危険な場所などを探索しました。その後、現地調査の内容をまとめ、危険箇所の写真を貼り付けた地図を作成。研修生は小宮教授と同研究室の学生にアドバイスを受けながら、熱心に取り組んでいました。
 各班の地図発表を聞いた小宮教授は、地図の完成度に感心しながら「今日1日で、多くのみなさんが犯罪の起こりやすい場所を見分ける力をつけた。それぞれの地域でこの取り組みを広げてほしい」と講評。研修生らも「安全マップは一度作って終わりにしてはダメ」「家族や地域で話し合うことが大切」と話し、安全・安心なまちづくりの推進を約束しました。 各班の地図発表を聞いた小宮教授は、地図の完成度に感心しながら「今日1日で、多くのみなさんが犯罪の起こりやすい場所を見分ける力をつけた。それぞれの地域でこの取り組みを広げてほしい」と講評。研修生らも「安全マップは一度作って終わりにしてはダメ」「家族や地域で話し合うことが大切」と話し、安全・安心なまちづくりの推進を約束しました。 |
| |

