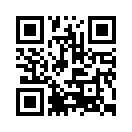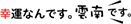市長所信表明(3月定例会)市長所信表明の全文の掲載しますのでご覧ください。
 市長所信表明(3月定例会)
市長所信表明(3月定例会)
令和6年度雲南市議会3月定例会開会に際し、市長の述べました「所信表明」の全文を掲載しますので、ご覧ください。
所信表明全文
令和7年雲南市議会3月定例会の開会にあたり、諸議案の説明に先立ちまして、市政における私の基本的な考え方を申し上げ、市議会の皆様並びに市民の皆様のご理解とご協力を賜りたいと存じます。
このたび多くの市民の皆様から温かいご支援をいただき、雲南市長として2期目の市政を担うこととなりました。改めて、市長としての重責に身の引き締まる思いであり、本市が直面する人口減少対策をはじめとする様々な課題に果敢に取り組んで参る所存であります。また、先般の市議会臨時会におきましてご同意をいただきました西村 健一副市長が今月4日より新たに就任いたしました。副市長、教育長共々、粉骨砕身、全力で職務を全うすることを改めてお誓い申し上げますとともに、市議会の皆様、市民の皆様の引き続いてのご協力を賜りますようお願い申し上げます。
最初に、市政運営に臨む基本的な政治姿勢についてであります。
これまで市議会をはじめ、市政懇談会や意見交換会、さらに地域行事への参加など、市民や地域の皆様から直接ご意見を聴く場、対話の場をもちながら、市民本位の行政運営に努めて参りました。こうした基本姿勢を大切にしながら、これまで力を入れてきた人口減少対策、農業・産業の振興、広域観光、デジタル化の推進や脱炭素社会の実現に向けた取り組みに加え、行財政改革を進めながら、将来を見据えた施策を着実に推進し、多くの皆様に「住みたい」、「住んでよかった」と思われるまちづくりに取り組んで参ります。
次に、市政運営に臨む重点課題についてであります。
まず、第3次雲南市総合計画の推進について述べます。
令和7年度から10年間のまちづくりの指針となる第3次雲南市総合計画がスタートいたします。本計画は、総合計画策定委員会や市議会の皆様をはじめ、市民ワークショップやタウンミーティングなど、様々な場面での対話を通じて得られたご意見を基に、『市民の計画』として取りまとめたところです。この計画では、みんなが幸せに暮らせる持続可能なまちの実現をめざし、「えすこな 雲南市」を将来像に掲げております。「えすこに暮らす」、「えすこに育む」、「えすこに創る」の3つの観点を共通軸に据え、12の施策を分野横断で展開しながら、市民一人ひとりが幸せを実感していただけるよう、取り組んで参ります。
これまでの人口減少対策の着実な取り組みにより、移住希望者向け雑誌の「住みたい田舎ランキング」において、4年連続で部門別全国第1位を獲得するなど引き続き高い評価をいただいている中で、近年、人口の社会動態が改善傾向にあると認識しております。そうした中でも、県外進学者のUターンが弱いことは引き続く課題であり、市内高校卒業生とのつながりづくりや市内就職のマッチング支援体制の構築などを進めて参ります。また、地域おこし協力隊制度の積極的な活用、季節に応じて複数の仕事に従事する「特定地域づくり協同組合」の増員などにより移住定住対策の推進に積極的に取り組みます。さらに移住だけでなく、多様な暮らし方ができるよう、二地域居住やお試し暮らしができる環境づくりを進め、関係人口の増加も促進して参ります。
国においては、石破政権の肝いり施策として、新たな「地方創生2.0」の構想づくりが始まり、その基本的な考え方として「当面は人口・生産年齢人口が減少する事態を正面から受け止めたうえで、社会を機能させる適応策を講じる」との方向性が示されました。本市においても10年後には人口27,000人程度と推計されており、人口が減少しても地域がしっかりと維持・継承されていくよう、様々な適応策を講じていく必要があります。これまで大切にしてきた「協働」、「チャレンジ」をさらに発展させ、関係人口や民間資金を効果的に取り込みながら、まちづくりを進めて参ります。さらに、地域の人権意識を高め、性別、国籍、年代、障がいの有無など、様々な違いをお互いに認め合い、地域の一員として自分らしく暮らすことができる地域共生社会の実現に向け、みんなが幸せに暮らせる「えすこな雲南市」をめざし取り組んで参ります。なお、手話をはじめとする障がい者の方の多様なコミュニケーション手段の普及等を図るため、条例制定に向けた検討を進めているところであります。
次に、物価高騰対策についてであります。
長引くエネルギーや消費者物価価格の高騰は、市民生活や企業活動等に大きな影響を与えており、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用した支援を行って参ります。
生活支援としての住民税非課税世帯に対する1世帯3万円給付事業については、本年1月に補正予算を専決したところであり、可能な限り早期の支給を行って参ります。
高齢者福祉施設、障害者福祉施設、医療機関、児童福祉施設及び市内施設の指定管理者に対しては、原油価格、物価高騰の経済的な影響を抑制し、継続的・安定的に医療及びサービスが提供できるよう支援金を支給して参ります。
物価高騰等の影響を受ける市内事業者の事業継続や市内経済の活性化のため、事業者自らが実施する消費喚起活動、生産性向上、販路開拓等に向けた取り組みに対し、その経費の一部を支援して参ります。
物価高騰により減退する消費喚起策として、令和7年度も引き続き雲南市プレミアムカタログ、及び宿泊者向けプレミアム付うんなん観光券を実施いたします。これにより市内経済の活性化を図って参ります。
今後も国・県の経済対策の動向や市民生活や市内の経済状況などに注視しながら、必要な支援や地域経済の活性化策を検討して参ります。
次に、豪雨災害に対する復旧状況についてであります。
令和3年以降、公共施設、農地、農業用施設を合わせ、923箇所の災害復旧工事を実施して参りましたが、令和5年までに発生した災害復旧工事につきましては、令和7年度中の完了を見込んでおります。また、令和6年に発生した62箇所の災害につきましても、早期の完了をめざして参ります。なお、市道多久和六重線の災害復旧工事はすでに着手しており、大仁広域農道の久野地内の復旧工事につきましては、今議会に契約議決の承認を求める追加議案を提出する予定としております。
次に、行財政改革の推進についてであります。
金利や物価・賃金上昇等の影響を受け、今後も人件費や公債費等の義務的経費や委託料等の増加が見込まれております。一方で、本市の一般財源収入の大半を占める地方交付税については人口の減少に伴い減少し、また、全国的に税収が伸びる中で中小企業の多い地方においては、税収が伸び悩む状況であり、一般財源の収支不足が拡大することが見込まれています。今後5年間の財政状況を示す中期財政計画においては、この収支不足を補うため、財政調整基金、減債基金のほか、特定目的基金の繰り入れも行わざるを得ない見通しとなっております。今後、健全財政を維持していくためには、公共施設の適正化、事業の見直しを徹底して取り組むとともに、行政組織の見直し、デジタル化による業務の効率化、ふるさと納税などによる歳入の拡大など、行財政改革を一層推し進める必要があります。持続可能な財政運営を確保するため、市民の皆様のご理解をいただきながら、市政運営にあたって参ります。
次に、第3次雲南市総合計画に掲げる「えすこに暮らす」、「えすこに育む」、「えすこに創る」の3つの柱に沿って申し述べます。
最初に、「えすこに暮らす」に関することについてであります。
まず、地域の担い手対策について述べます。
地域活動における担い手対策は、持続可能な地域づくりへ向けた最重要課題の一つであります。各地域自主組織では、担い手育成補助金の活用により、若者世代等の参画を意識した取り組みが展開されているところですが、引き続き、この補助金による取り組み支援を継続するとともに、地域経営カレッジの開催などにより、次世代の地域づくりへの関わりを推進して参ります。また、昨今の賃金水準の上昇や人材確保が困難となっている状況を考慮し、地域自主組織への交付金の算定にあたっては、給料のベースアップ等を可能とするため、現下の賃金水準の引き上げを勘案した増額を行う方針としております。地域自主組織の職員確保対策の一助となることを期待しているところですが、これに留まらず、どのような方策を講じていくべきか、引き続き地域自主組織の皆様とともに検討して参ります。
続いて、交流センターの整備についてであります。
幡屋交流センター整備事業につきましては、今年度から基本設計等に着手しており、令和7年度においては実施設計のほか、既存施設の解体及び敷地造成工事等を実施する予定としております。今後も事業の進捗を図りながら、令和9年度までの建設工事完了に向けて進めて参ります。
続いて、木次線の利用促進に向けた取り組みについてであります。
観光列車「あめつち」の今シーズンの運行が3月23日から始まることとなり、地元ガイドによる列車内での観光案内や特産品販売、駅舎でのおもてなしを引き続き行って参ります。周遊観光策につきましては、沿線自治体、観光事業者等と連携し、JR木次線を活用した観光ツアーの造成を進めるとともに、JR木次線を利用した旅行助成事業の予算額を増額するなど、積極的に取り組んで参ります。また、日常利用の促進策につきましては、昨年度より高校生の通学を対象として実施している、バスから鉄道への転換を目的としたバスに無料で乗れる取り扱いについても、対象を高校生以外にも拡充いたします。さらに、木次線応援団の会員数が200名を超えたところであり、会員の皆様に向けた情報提供やイベントへの参加の呼びかけなどにより、一緒に木次線を盛り上げていただけるよう、さらなる利用促進並びに魅力の創出に取り組んで参ります。
続いて、空き家対策についてであります。
市内全域で空き家が増加しており、令和5年の住宅・土地統計調査によると市内の空き家数は1,660戸と、5年前の同調査から260戸増加し、今後も増加することが懸念されます。この要因の一つとして、住宅除却後の宅地は、固定資産税の課税の特例が解除されることとなり、固定資産税が増額するということがあります。この問題を解消するため、住宅除却後も固定資産税を最大3年間減免する制度を創設いたします。これにより、空き家を含む未利用住宅の除却が促進され、周辺の生活環境が保全されるとともに、土地の有効活用が図られ、「まち」や「地域」の活力の維持・向上につながることを期待するものであります。
一方で管理不全の空き家については、所有者に対し情報提供や助言を行うとともに、必要に応じて空き家法に基づく指導・勧告などの行政手続きを厳正に実施し、適正管理されるよう対応して参ります。
続いて、防災対策についてであります。
近年頻発する豪雨災害に対して、水害による被害の軽減を図るため、国土交通省及び島根県では、想定し得る最大規模の降雨により当該河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域を洪水浸水想定区域として指定し公表を行ってきています。この度、島根県の管理する中小河川において指定区域が示されることから本市におきましても、新たな指定区域を反映し、併せて適切な避難行動や手順など分かりやすく記載したハザードマップの更新に取り組んで参ります。
また、各地の災害対応等による知見を踏まえ、諸計画の見直しや計画的な備蓄を進め、各種防災講座の実施、地域自主組織の皆様と協働による防災訓練の実施など、引き続き防災に係る対策を推進して参ります。
続いて、原子力防災についてであります。
島根原子力発電所2号機につきましては、本年1月10日に営業運転が再開されたところです。本市といたしましては、これまで原子力規制委員会による審査状況を注視するとともに、安全対策工事に伴う機器据付や性能試験、起動前準備や原子炉起動など、運転再開までの主要なタイミングで他の関係自治体と合同で都度現場に立ち会い、機器操作や検査等の状況確認を7回にわたって行って参りました。その際、中国電力に対して工程ありきではなく、安全を最優先して進めるよう求めてきており、今後とも、安全を大前提に取り組んでいただくよう求めて参ります。
また、本年度の原子力防災訓練のうち、地震との複合災害を想定した初動対応訓練を今月6日に行いました。昨年11月23日に行った住民避難訓練を含めた訓練評価などにより、今後、島根県とも連携し、避難計画のさらなる充実を図っていくとともに、避難ルートマップの検証を行っていく考えであります。さらに、1号機の廃止措置及び3号機の設置変更許可並びに放射性廃棄物の処理に係る事業の状況等も確認していく考えであります。
引き続き、原子力防災対策にしっかりと取り組んで参ります。
続いて、「第5次雲南市総合保健福祉計画」、「第5次雲南市健康増進実施計画」及び「第4次雲南市食育推進計画」についてであります。
令和7年度から5年間を計画期間とする「第5次雲南市総合保健福祉計画」、「第5次雲南市健康増進実施計画」及び「第4次雲南市食育推進計画」を今年度内に策定し、こどもから高齢者まで、地域共生社会の実現に向け保健・医療・福祉における包括的な取り組みや持続可能な地域づくりを進め、市民誰もが健康で生涯を通じて安心して暮らせるよう、それぞれの計画に基づく取り組みを進めて参ります。
続いて、「うんなん愛の減塩プロジェクト」についてであります。
国が定める1日当たりの食塩相当量の目標は、成人男性が7.5グラム未満、女性が6.5グラム未満と設定されていますが、本市の令和6年度塩分摂取量は 9.2グラムと、国の目標値を大幅に超えている状況にあります。そこで、令和2年度から5年間にわたり、島根県からモデル地区に指定された幡屋地区において、大東町幡屋地区振興会とともに、“しまね健康寿命延伸プロジェクト”に取り組んだ結果、2グラムの減塩を達成することができました。健康教室で楽しく学ぶ減塩クイズの開催、フードモデルやのぼり旗を活用した啓発などにより、減塩意識が高まった成果であると評価をいただいております。こうした活動を「うんなん愛の減塩プロジェクト」と称して市内に広げ、市民の皆様が暮らしの中で楽しみながら減塩行動を実践していただくための取り組みを推進して参ります。
続いて、雲南市高齢者補聴器購入費助成についてであります。
高齢化の進展に伴い、認知症患者の増加と医療費の増大が見込まれる中、身体障害者手帳の交付対象とならない中等度難聴の高齢者に対し、補聴器の購入費用の一部を助成する制度を創設いたします。この助成により、高齢者の日常生活におけるコミュニケーションを支援し、積極的な社会参加を促すことによる認知症の予防を推進して参ります。
次に、「えすこに育む」に関することについてであります。
まず、子育て支援の充実について述べます。
令和5年度から進めている木次子育て支援センターの建設につきましては、順調に建設工事が完了し、本年3月17日から新たな施設で業務を開始する予定としております。また、令和7年4月1日から斐伊保育所及び木次子育て支援センターの運営方法を業務委託とし、保育サービスの拡充を図って参ります。さらに、佐世小学校区内において、させ児童クラブを新たに開設し、児童クラブの待機児童の解消を図って参ります。
続いて、大東公園サッカー場の整備についてであります。
大東公園サッカー場の整備につきましては、順調にグラウンド整備の工事を進めているところであり、この工事に合わせ照明設備や排水設備の整備も行う予定としております。本年5月に、ポット苗での芝の植えつけをスポーツ少年団や市民の皆様と協働で実施する計画としており、より多くの皆様に参加を呼びかけ、市民の皆様に愛着のある施設となるよう整備を進めて参ります。
続いて、令和7年度全国高等学校総合体育大会レスリング競技の開催についてであります。
本年7月27日から30日にかけて、三刀屋文化体育館アスパルで令和7年度全国高等学校総合体育大会レスリング競技の開催が予定されており、大会期間中には、6,000人を超える選手や関係者などが本市を訪れると見込んでおります。本市といたしましては、選手の皆様が実力を発揮される環境づくりはもとより、大会に関わる全ての皆様が、また雲南市に来たいと思っていただけるよう、実行委員会を中心に市内の高校や地域、商工関係者などの皆様と連携して取り組んで参ります。 なお、教育委員会内にスポーツ振興担当管理監として、レスリングの元オリンピック選手で日本代表のコーチを歴任された嘉戸 洋氏をこの4月から採用し、インターハイや国スポ全スポを契機とした、より一層のスポーツ振興を図って参ります。
続いて、教育基本計画の策定についてであります。
昨年6月から、雲南市教育基本計画策定委員会での協議を経て、令和7年度から5年間を計画期間とする「第5次雲南市教育基本計画」を今年度内に策定いたします。本計画は、本市の教育施策の基本的な方向性を示すものであり、併せて「雲南市教育大綱」に位置付けられるものとなります。「ふるさとを愛し 心豊かでたくましく未来を切り拓く 雲南市の人づくり」を引き続き基本目標として掲げ、その実現に向けてキャリア教育をより一層推進するとともに、本市の特色である地域資源を活用した教育を進めて参ります。また、地域社会との連携を深め、持続可能な地域づくりを進める人材の育成に重点を置き、具体的な目標として「学ぶ力と創造力を高め、豊かな人間性を持つ人づくり」と「学校・家庭・地域の連携・協働による教育環境づくり」を掲げており、これらの目標達成に向け、施策を展開して参ります。
続いて、木次中学校改築事業の進捗状況についてであります。
木次中学校の改築につきましては、雲南市立木次中学校整備検討委員会において基本計画の策定に向けて、施設の現況調査や児童生徒、教職員、保護者及び地域住民等を対象としたアンケート意向調査等から今後の課題を整理するとともに、基本理念及び施設整備方針について検討していただきました。今後、関係者や検討委員会のご意見をお聴きしながら、基本計画の策定に向けて取り組んで参ります。
続いて、旧海潮中学校校舎の利活用についてであります。
旧海潮中学校校舎の利活用につきましては、保護者や地域、学校等と協議を進めてきた結果、昨年8月に「旧海潮中学校へ海潮小学校を移転する」ことを利活用方針としてまとめたところです。移転時期につきまして、当初は改修工事の期間等を考慮し、令和8年9月を予定しておりましたが、早期の移転を望む意見が多く寄せられたことから、本年9月に前倒しすることといたしました。今後も、関係者と連携しながら円滑な移転整備を進めて参ります。
続いて、令和6年度北方領土に関する全国スピーチコンテストにおける北方対策担当大臣賞の受賞についてであります。
今月22日に東京都内で開催された令和6年度北方領土に関する全国スピーチコンテストにおいて、三刀屋中学校3年生の原 向日葵さんが「知る、繋ぐ、変える」と題して発表され、最優秀賞にあたる北方対策担当大臣賞を受賞されました。
このコンテストは、全国5千点を超える応募の中から選考され、原さんは昨年度も審査委員特別賞を受賞されており、2年連続での受賞となる快挙であります。
心よりお祝いいたしますとともに、益々のご活躍を期待しております。
続いて、学校と地域が連携し、子どもたちの学びを支える取り組みに対する文部科学大臣表彰についてであります。
学校と地域が連携・協働し、地域とともにある学校づくりや学校を核とした地域づくりに効果を上げている取り組みとして、木次地区学校運営協議会の取り組みが、令和6年度文部科学大臣表彰を受賞することとなりました。これは、「地域へGo toボランティア」と題した中学生の地域行事等へのボランティア参加とそれを通じた学校と地域、家庭の連携意識の醸成が高い評価を得たものであります。今後も、このような取り組みを推進し、学校と地域が連携・協力して、子どもたちを育む環境づくりを進めて参ります。
続いて、大東高校の寄宿舎の運営開始についてであります。
大東高校におきましては、大東町内に民間の空き家と市の定住促進住宅の空き室を寄宿舎として整備しているところですが、令和7年度の入学予定者のうち、県外及び市外から10名の入居希望がありました。これにより令和7年4月から2か所の寄宿舎の運営を開始することが確定し、現在、学校や地域の皆様と連携して開設の準備を進めているところであります。
今後は、この寄宿舎が大東高校の魅力を高め、新たな交流や賑わい創出にも寄与できるよう、地域とともにある寄宿舎をめざして参ります。
次に、「えすこに創る」に関することについてであります。
まず、中山間地域等直接支払制度について述べます。
中山間地域等直接支払制度は、第6期対策として令和7年度から5年間の対策が始まります。この制度の変更点といたしましては、複数の集落協定による連携や統合など多様な組織等への参画に関する「ネットワーク化活動計画」の作成、ネットワーク化やスマート農業の導入などの取り組みに対する加算制度が創設されることとなりました。また、令和7年度は多面的機能支払制度も第3期の対策が開始されることに伴い、多数の活動組織が再認定時期であり、中山間と多面的の説明会を各総合センター単位で行います。引き続き、事務の省力化、組織体制の強化を図っていくため、集落協定及び活動組織の広域化を推進して参ります。
続いて、農業振興についてであります。
農作物の振興につきましては、本市のブランド米「プレミアムつや姫たたら焰米」の認定率向上をめざし、栽培指導などを強化し、より一層の品質向上を図ります。また、良質で安全・安心な地元産米としてのブランド力を高めるとともに、販売を強化し、生産者の所得向上をめざします。昨年からの米価格の急騰は、生産者の意欲の増進につながっております。こうした状況は、農作物価格の適正化に向けた大きな一歩であると考えており、生産者の経営安定化による担い手確保や作付面積の拡大が進むことを期待するところであります。
園芸振興につきましては、令和7年度から新規青年就農者が、新たに県推奨6品目のひとつであるアスパラガス栽培に取り組まれることとなり、今後のさらなる園芸振興に期待するものであります。また、産直関係では、現在、出雲市内の大型ショッピングセンター及びスーパーマーケットの2店舗で野菜等の販売を行っておりますが、さらに令和7年度からは、広島県のスーパーマーケットにおいても雲南市産の農産物の販売がスタートいたします。こうした機会を捉え、今後一層の販売拡大を図って参ります。
担い手対策につきましては、先般、本市で27番目となる農事組合法人八所が設立されたところでありますが、地域農業を担う意欲ある担い手として、認定農業者の育成や確保、集落営農の組織化や法人化、経営規模の拡大などの経営体質の強化に引き続き取り組んで参ります。
耕作放棄地対策につきましては、少ない労働力で栽培できる蕎麦や米粉用米などの土地利用型作物を引き続き推進するとともに、産地化を進めている山椒の栽培面積を拡大しながら、耕作放棄地の抑制に努めます。さらに耕作放棄地の拡大防止に向けては、集落営農等の担い手の育成・確保や営農の維持・継続に対する支援に取り組んで参ります。一方、耕作を諦められた農地に対し、新たな担い手がすぐに見つからない状況もあり、防災・環境保全の観点からも、さらなる対策が必要と考えております。今後、耕作が休止されてから、次の担い手が見つかるまでの間、農地を管理する新たな仕組みづくりについて検討を進めて参ります。
畜産振興につきましては、畜産業従事者が減少する中、繁殖農家の担い手確保対策など、雲南地域の和牛振興に向けた取り組みを進める必要があります。そのため、その基本となる方針や施策の方向性を示す「雲南地域和牛振興ビジョン」により、「奥出雲和牛」ブランドの産地の維持、価値の向上対策及び担い手対策につながる事業に取り組んで参ります。
続いて、農作物の有害鳥獣対策についてであります。
イノシシ対策につきましては、駆除・防除に引き続き取り組んでいくとともに、被害が拡大傾向にあるサル被害対策について、市猟友会のご協力を得て、大型・小型檻、くくり罠による捕獲やGPS装置、ドローンを活用した行動把握による駆除・防除活動など、その効果を検証しながら対策の強化を図って参ります。さらに、ニホンジカ対策につきましては、島根県、奥出雲町、飯南町と連携した広域駆除活動に取り組み、被害の拡大防止に努めて参ります。
続いて、林業振興についてであります。
森林環境譲与税を活用し、レーザー計測データを用いた森林資源の解析により森林整備を進め、さらには林業の担い手確保や木材利用の推進など、川上から川下までの一体的な支援をめざしてきたところです。引き続き、この財源の活用により、林業振興ビジョンの実現に向けた取り組みを推進し、森林GISデータの活用とDX化による森林施業の効率化や、経営管理が可能な森林の団地化と担い手への集約化を図るとともに、所有者不明の森林等の対策も進めて参ります。
また、広葉樹利用の推進、製材品の販路開拓と利用拡大、林業従事者の技術向上を図る研修会の開催など、関係する企業・団体と連携を図り、森林整備、木材利用、人材育成に幅広く、そして積極的に取り組んで参ります。
続いて、第3次雲南市産業振興ビジョンについてであります。
令和7年度から10年間の第3次雲南市産業振興ビジョンの策定に向けて、雲南市地域経済振興会議でご検討いただくとともに、市議会の皆様からのご意見も踏まえ、ビジョン案を作成いたしました。現在、パブリックコメントにより、市民の皆様のご意見を伺っているところであり、「挑戦し、活力を産みだす雲南市」を基本理念として、本市の商工業振興を推し進めていくための重要な指針となるよう策定を進めて参ります。
続いて、神原企業団地の整備についてであります。
雲南加茂スマートインターチェンジへのアクセスの良さを強みとして、神原企業団地の整備を進めております。第2期B工区造成事業につきましては、令和7年度から土砂の搬出を予定しており、引き続き関係機関と連携を図りながら、着実な事業実施に努めて参ります。
続いて、観光振興についてであります。
本市の桜まつりは2月から4月まで3月にわたり楽しめることから、例年市内外から多くの皆様にご来訪いただいております。今年の桜まつりのメインイベントとして、本市の食を堪能いただく雲南食堂を4月5日、6日の両日にJR木次駅前周辺で開催いたします。桜に合わせて、本市の魅力をしっかりと発信して参ります。
観光誘客に向けた二次交通対策につきましては、従来からの課題である出雲空港からの移動手段の確保対策として、予約制タクシーの運行と宿泊者向けのレンタカー利用料助成に取り組みます。いずれも本市への誘客を促進する効果的な取り組みであると考え、まずは試行的に実施し、実績を把握・分析しながら利用者のニーズに合った施策となるよう検討して参ります。
続いて、市有施設の民間譲渡についてであります。
吉田グリーンシャワーの森につきましては、民間の活力を活かした観光振興を図るため、今月18日に株式会社たなべたたらの里との譲渡に関する仮契約を締結いたしました。今後10年間は観光振興サービスを指定用途とし、その間施設リニューアルによって観光の魅力が向上することを期待して、無償譲渡としており、今議会に追加議案として関係する議案を提出する予定としております。
続いて、脱炭素社会実現に向けた取り組みについてであります。
今年度は雲南市脱炭素社会実現計画の1年目として、再生可能エネルギーの導入に向け、市内を拠点とする地域エネルギー会社を公募により選定したところであり、令和7年度からは、まずは公共施設への太陽光発電導入に向け、具体的な準備を進めていくこととしております。また、省エネの推進につきましては、電気自動車用の充電設備を市役所本庁舎や市立病院、道の駅などの公共施設15か所に設置いたしました。スマートフォンでの料金支払いの仕組みにより民間主導で行うものですが、今後も民間事業者と連携し、設置個所を順次拡大していく考えであります。
ごみの減量化につきましては、キエーロコンポストの普及に加え、廃食油の回収も試行的に実施しており、この取り組みをさらに推進していくため、今月から資源循環コーディネーターとして地域おこし協力隊を配置したところであります。
このほか様々な取り組みを進めておりますが、計画2年目となる令和7年度においても、市民の皆様や事業者の皆様とともに、着実に計画の実現に向けて取り組んで参ります。
最後に「行政経営」についてであります。
まずは、令和7年度の組織見直しについて述べます。
社会情勢の変化や多様化する市民ニーズに対応し、持続可能な行政サービスを将来にわたって維持するため、行財政改革を強化いたします。また、細分化した組織の見直しや効率的な組織体制を構築するなど、組織機構の見直しを行います。
公共施設の見直しや業務効率化及び行政DXなどのさらなる行財政改革を推進するため、総務部内の「行財政改革推進室」を「行財政改革推進課」へ改組いたします。同じく総務部内の「災害復興調整室」につきましては、令和3年7月豪雨災害の復興に一定の見通しが立ったことから廃止とし、同室の業務につきましては、建設部内の「建設工務課」及び「農地整備課」に移管します。
新型コロナワクチンの定期接種化に伴い、臨時的措置として設置しておりました健康福祉部内の「予防接種対策室」を、同部内の「健康推進課」に統合いたします。
こども政策局所管の「斐伊保育所」につきましては、保育業務委託を導入し、多様化する保育ニーズに適応した保育機能の充実を図ります。また、同保育所の狭あい対策として移転新築した「木次子育て支援センター」につきましても、業務委託を導入し、地域の子育て支援機能の維持・充実を図ります。
産業観光部内の「観光振興課」につきましては、雲南市観光協会との事務所一体化により連携強化を図り、効率的で効果的な観光振興体制を構築いたします。また、同じく産業観光部内の「広域観光・インバウンド推進室」を、同部内の「観光振興課」に統合します。同じく産業観光部内の「産業施設課」と「観光施設再生活用推進室」を統合し、名称を「産業観光総務課」に改め、予算や観光施設等の管理業務について効率化を図ります。
本市と雲南市土地開発公社が一体的に業務に取り組める体制を整えるため、建設部内の「都市計画課」に土地開発公社の職員を配置し、さらなる連携強化を図ります。
学びの保障に向けた不登校支援について、所管課の一元化を図るとともに、特別支援との連携を図るため、教育委員会内に「児童生徒支援課」を新たに設置いたします。
続いて、令和7年度一般会計当初予算及び令和6年度3月補正予算についてであります。
まず、令和7年度一般会計当初予算について述べます。
令和7年度の国の地方財政計画では、財源総額は人件費の増加や物価高が見込まれる中、地方の一般歳出は3.6パーセント程度の増加とされていますが、地方交付税は1.7パーセントの増加にとどまり、地方税収の増加により一般財源が賄われる計画となっております。そうした中で、中小企業が多く地方税の伸びに多くを期待できない当市においては、極力歳出の抑制に努めた予算編成とし、対前年度 5.5パーセントの減として編成したところです。また、合併特例債の適用期限終了、過疎債の確保の見通しなどを踏まえつつ、将来負担の低減を図るための起債発行額の抑制を図ったところであり、今後の財源確保の状況に応じて補正予算等で対応していく考えであります。そうした中でも、本市の令和7年度一般会計当初予算につきましては、「第3次雲南市総合計画」に基づく持続可能なまちづくりの推進を最重要課題として調整するとともに、長期化する物価高等への対策経費を盛り込んだ予算措置を行ったところです。
次に、令和6年度3月補正予算についてであります 。
一般会計では、各種事業補助金返還金6千3百万円、退職手当特別負担金3千9百万円余などを追加計上し、特別会計等では、国民健康保険事業特別会計、工業用水道事業会計、下水道事業会計及び病院事業会計で、それぞれ事業内容の変更等に伴う予算を計上しております。
その外、議案として、条例18件、一般事件8件、諮問事項2件を提出しておりますので、慎重にご審議いただき、可決賜りますようお願い申し上げます。
以上、市政運営に臨む所信の一端を申し述べ、開会にあたってのご挨拶といたします。
令和7年2月28日
雲南市長 石 飛 厚 志
 お問い合わせ先
お問い合わせ先
- 政策企画部 政策推進課
- 〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1 - Tel 0854-40-1011
- Fax 0854-40-1029
- seisakusuishin@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。

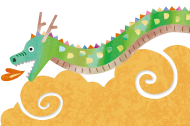

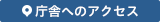

 妊娠・出産
妊娠・出産 子育て
子育て 学校・教育
学校・教育 結婚・離婚
結婚・離婚 住まい・引越し
住まい・引越し 就職・退職
就職・退職 高齢者・介護
高齢者・介護 お悔やみ
お悔やみ

 利用者別メニューから探す
利用者別メニューから探す







 お問い合わせはこちら
お問い合わせはこちら