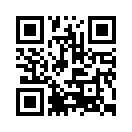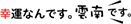ひとり親家庭等に対する助成制度「児童扶養手当」児童扶養手当の支給について。(外国人の方についても支給の対象となります。)
 児童扶養手当の詳細
児童扶養手当の詳細
児童扶養手当は、父母の離婚などにより父または母と生計をともにしていない児童を監護・養育している人に対し、児童の健やかな成長を願って支給される手当です。(外国人の方についても支給の対象となります。)
児童扶養手当を受けることができる人(支給要件)
手当を受けることができる人は、次の条件に当てはまる18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を監護している母、父(父の場合は、生計を同じくしていることが必要)または父母に代わってその児童を養育している人(養育者)です。
なお、児童が心身におおむね中度以上の障がいのある場合は、20歳になる日の前日が属する月分まで手当が受けられます。
- (1)父母が離婚した児童
- (2)父または母が死亡した児童
- (3)父または母が障がいの状態にある児童(別表を参照)
- (4)父または母の生死が明らかでない児童
- (5)父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
- (6)父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- (7)父または母が法令等により引き続き1年以上拘禁されている児童
- (8)婚姻によらないで生まれた児童
- (9)棄児などで父母がいるかいないかが明らかでない児童
※いずれの場合も国籍は問いません。
児童扶養手当を受けられない人
次のいずれかに該当するときは、この手当は支給されません。
児童が
- (1)日本国内に住所がないとき
- (2)児童福祉施設などに入所しているとき、または里親に委託されているとき
- (3)母の配偶者(事実婚も含む)に養育されているとき(父が重度障がい者の場合を除く)
- (4)父の配偶者(事実婚も含む)に養育されているとき(母が重度障がい者の場合を除く)
母、父または養育者が
日本国内に住所がないとき
児童扶養手当の月額
| 区分 | 児童1人 | 児童2人目以降加算額(ひとりにつき) |
|---|---|---|
| 全部支給 | 46,690円 | 11,030円 |
| 一部支給 | 46,680円~11,010円 | 11,020円~5,520円 |
- ※一部支給額は所得額に応じて、10円きざみの額となります。
- ※手当額は全国消費者物価指数の動向に合わせて改定されます。
- ※一部支給停止について
- 手当の受給開始月から5年または支給要件に該当した月から7年を経過したときは、手当額の2分の1が支給停止されます。ただし、就業していることなどの一定の事由に該当する場合は、必要な書類を提出していただければ、一部支給停止の適用除外となります。
所得制限の限度額
前年の所得(年間の収入金額から給与所得控除などを控除した額)が下表の額以上であるときは、その年度(11月から翌年の10月まで)の手当の一部または全部が停止になります。
| 扶養親族等の数区分 | 前年分所得 (ただし、1月から9月までに請求する場合は前々年所得) |
|---|---|
| 0人 | 69万円 |
| 1人 | 107万円 |
| 2人 | 145万円 |
| 3人 | 183万円 |
| 4人以降は1人につき | 38万円ずつ加算 |
| 扶養親族等の数区分 | 前年分所得 (ただし、1月から9月までに請求する場合は前々年所得) |
|---|---|
| 0人 | 208万円 |
| 1人 | 246万円 |
| 2人 | 284万円 |
| 3人 | 322万円 |
| 4人以降は1人につき | 38万円ずつ加算 |
| 扶養親族等の数区分 | 前年分所得 (ただし、1月から9月までに請求する場合は前々年所得) |
|---|---|
| 0人 | 236万円 |
| 1人 | 274万円 |
| 2人 | 312万円 |
| 3人 | 350万円 |
| 4人以降は1人につき | 38万円ずつ加算 |
限度額に加算されるもの
- 請求者(本人)の場合
- 同一生計配偶者・老人扶養親族がある場合は1人につき10万円
- 特定扶養親族・控除対象扶養親族がある場合は1人につき15万円
- 扶養義務者等の場合
- 老人扶養親族がある場合は1人につき6万円
(ただし、扶養親族等がすべて70才以上の場合は、1人を除く)
所得額の計算方法
所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額)+養育費(※1)-100,000円(※2)-80,000円-下記の控除
諸控除の額(主なもの)
- 障がい者控除・勤労学生控除 270,000円
- 特別障がい者控除 400,000円
- 配偶者特別控除・医療費控除等 地方税法で控除された額
請求者(本人)が母または父の場合、寡婦控除・ひとり親控除の適用なし
(※1)養育費・・・児童の父または母から、その児童について扶養義務を履行するための費用として受け取る金品等でその金額の8割
(※2)給与所得および公的年金に係る所得を有する方は、その合計額から最大10万円控除します
児童扶養手当の支給
手当は、認定されると請求された月の翌月分から支給されます。
支給は、年6回に分けて2ヶ月分の手当が請求者の預金通帳の口座に振り込まれます。
| 支給予定日 | 支給対象月 |
|---|---|
| 令和7年5月9日(金) | 3月分・4月分 |
| 7月11日(金) | 5月分・6月分 |
| 9月11日(木) | 7月分・8月分 |
| 11月11日(火) | 9月分・10月分 |
| 令和8年1月9日(金) | 11月分・12月分 |
| 3月11日(水) | 1月分・2月分 |
児童扶養手当を受ける手続き
市役所子ども家庭支援課または各総合センターで請求の手続きをしてください。
持参いただくもの
1.戸籍謄本(請求者と対象児童のもの)
2.口座番号のわかるもの
3.年金手帳
4.受給者、対象児童、扶養義務者の個人番号のわかるもの
5.受給者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
請求に必要な添付書類
| 支給要件 | 添付書類 |
|---|---|
| 共通 | 1 請求者および対象児童の戸籍謄本または抄本 2 請求者および対象児童の属する世帯全員の住民票の写し (注意) (1)続柄・本籍等の記載を省略したものは不可 (2)外国人の場合は在留カード ※(1)(2)については市町村において確認が可能な場合は、省略できる場合があります。 3 公的年金調書(市町村で作成します) 4 養育費に関する申告書(請求者が母または父の場合) |
| 離婚 | 事実婚解消の場合は事実婚解消に関する調書および申立書 |
| 父または母が死亡 | 父または母死亡の記載のある戸籍謄本または抄本 |
| 父または母に障がい | 障害認定診断書(障がい基礎年金の1級に該当する場合は、年金証書の写) |
| 父または母が生死不明 | 警察署、福祉事務所、その他官公署、関係会社等の証明書 |
| 遺棄 | 父または母が1年以上遺棄している事実を明らかにする遺棄調書および申立書 |
| DV | 保護命令決定書の謄本 および 確定証明書 |
| 父または母が拘禁 | 父または母が1年以上拘禁されている事実を明らかにする書類 |
| 未婚の父または母 | 事実婚解消等調書 |
(注)これらの書類以外にも個別の事情により必要となる書類があります。
手当を受けている人の届出
手当の受給中は次のような届出等が必要です。
- 届出が遅れたり、しなかったりすると、手当の支給が遅れたり、受けられなかったり、場合によっては手当を返還していただくこともありますので、忘れずに提出してください。
- 上記のほか、受給資格の有無および額の決定のため、書類の提出が必要となる場合があります。
ご注意!
次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますから、必ず速やかに資格喪失届を提出してください。届出をしないまま手当を受けていますと、その期間の手当を全額返還していただくことになります。
- 手当を受けている母または父が婚姻したとき(内縁関係、同居なども同じです)
- 対象児童を養育、監護しなくなったとき(児童の施設入所・里親委託・婚姻を含みます)
- 遺棄されていた児童の父または母が帰ってきたとき(父または母からの送金や安否を気遣う電話・手紙など連絡があった場合を含みます)
- 拘禁されていた児童の父または母が出所したとき(仮出所も含みます)
- 受給者である母の児童が父と生計を同じくするようになったとき
- 受給者である父の児童が母と生計を同じくするようになったとき
- その他受給条件に該当しなくなったとき
児童扶養手当証書
児童扶養手当証書は、児童扶養手当を受ける資格があることを証明する重要な書類です。大切に保管してください。
- (1)児童扶養手当証書の裏面には、児童扶養手当を受ける上で重要なことが書いてありますので必ず読んでおいてください。
- (2)証書は他人に譲り渡したり、質に入れたりすることはできません。
- (3)市町村の児童扶養手当の窓口へ届け出るときは、必ず証書を持参してくだい。
- (4)旅客鉄道会社の通勤定期乗車券の割引制度があります。(市町村窓口へ)
- (5)少額貯蓄非課税制度(新マル優制度)預貯金利子が一定の金額まで非課税となります。(金融機関窓口へ)
児童扶養手当を受給するにあたって
- 児童扶養手当の支給を受けた父または母は、自ら進んでその自立を図り、家庭の生活の安定と向上に努めなければなりません。
- 受給資格者(養育者を除く)が、正当な理由がなくて、就職活動や自立を図るための活動をしなかったときは手当が支給されなくなります。
- 偽りその他不正の手段によって手当を受けた者は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。
- 手当の認定の請求をした方又は受給資格がある方に対しては、相談に応じ、必要な情報の提供および助言を行います。
【別表】父または母が障がいの場合
- 次に掲げる視力障害
○両眼の視力がそれぞれ〇・〇三以下のもの
○一眼の視力が〇・〇四、他眼の視力が手動弁以下のもの
○ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/四視標による周辺視野角度の和がそれぞれ八〇度以下かつⅠ/二視標による両眼中心視野角度が二八度以下のもの
○自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が七〇点以下かつ両眼中心視野視認点数が二〇点以下のもの - 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
- 両上肢の機能に著しい障がいを有するもの
- 両上肢のすべての指を欠くもの
- 両上肢のすべての指の機能に著しい障がいを有するもの
- 両下肢の機能に著しく障がいを有するもの
- 両下肢を足関節以上で欠くもの
- 体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障がいを有するもの
- 前各号掲げるもののほか、身体の機能に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の介護を必要とする程度の障がいを有するもの
- 精神に労働することを不能ならしめ、かつ、常時の監視または介護を必要とする程度の障がいを有するもの
- 傷病が治らないで、身体の機能または精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の監視または介護とを必要とする程度の障がいを有するものであって、内閣総理大臣が定めるもの
 備考
備考
視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
※内閣総理大臣が定めるものとは、当該障がいの原因となった傷病につき、はじめて医師の診断を受けた日から起算して1年6か月を経過しているものをいう。(昭和60年厚生省告示第124号)
お知らせ
(1)平成26年12月から公的年金との併給見直しにより、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
現在、「障害基礎年金の子の加算」の支給を受けないで、児童扶養手当を受給している方については、「年金の子の加算」を受給するための手続きをしていただき、「年金の子の加算額」と児童扶養手当額の差額分を受給していただくこととなります。
(2)令和3年3月分(令和3年5月支払い)から児童扶養手当と調整する障害基礎年金等の範囲が変わりました。
これまで、障害基礎年金等(※1)を受給している方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。
(※1)国民健康法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など。
 お問い合わせ先
お問い合わせ先
- こども政策局 こども家庭支援課(こども家庭センター)
- 〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1 - Tel 0854-40-1067
- Fax 0854-40-1079
- kodomokateishien@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。

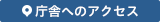

 妊娠・出産
妊娠・出産 子育て
子育て 学校・教育
学校・教育 結婚・離婚
結婚・離婚 住まい・引越し
住まい・引越し 就職・退職
就職・退職 高齢者・介護
高齢者・介護 お悔やみ
お悔やみ

 利用者別メニューから探す
利用者別メニューから探す







 お問合わせはこちら
お問合わせはこちら