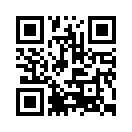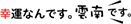個人住民税の概要個人住民税とは
個人住民税とは、一般的に個人市民税と個人県民税を合わせたもので、前年の1月1日から12月31日の1年間に得た所得に対して課税される税金です。その年の1月1日に居住している市区町村において課税されます。
住民税は主に所得金額が一定の基準以上の人が均等に負担する均等割額とその人の所得金額に応じて負担する所得割額とで成り立っています。
 詳細
詳細
1.納税義務者
1月1日に雲南市内に住所を有し、前年中に所得を有する人
2.課税されない人
- 生活保護法によって生活扶助を受けている人
- 障がい者、未成年者、寡婦およびひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の人
- 前年の合計所得金額が一定の基準以下の人
3.均等割額
| 市民税 | 県民税 | 森林環境税 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 3,000円 | 1,500円 | 1,000円 | 5,500円 |
※県民税のうち500円は「水と緑の森づくり税」です。
水と緑の森づくり税は、平成17年度から実施されており、令和2年度から5年間更に継続されることになりました。
※令和6年度より森林環境税(国税)の徴収が始まります。
詳しくは「森林環境税について」![]() をご覧ください。
をご覧ください。
4.所得割額
前年中の所得金額を基礎とし、次により計算した金額です。
課税所得金額(所得金額-所得控除額)×税率-税額控除等=所得割額
| 市民税 | 県民税 | 合計 |
|---|---|---|
| 6% | 4% | 10% |
※分離課税の所得については、個別に税率が定められています。
- 例)土地・建物等の譲渡所得
- 長期一般分 5%(市3%、県2%)、短期一般分 9%(市5.4%、県3.6%)
- 例)株式等の譲渡所得
- 未公開分等 5%(市3%、県2%)、上場分等 5%(市3%、県2%)
5.納期限
普通徴収の納期限(口座振替日) ※特別徴収(給与や公的年金からの天引き)を除く納付方法
| 期 別 | 納期限(口座振替日) |
|---|---|
| 第1期 | 6月末日 |
| 第2期 | 8月末日 |
| 第3期 | 10月末日 |
| 第4期 | 翌年1月末日 |
※月末が土日、祝日だった場合、翌営業日の期限となります。
※税額が5,500円(均等割)以下の場合は、全額を第1期に納付することになります。
6.税額の計算方法
→総所得金額①−所得控除合計②=課税総所得金額③
課税総所得金額③×税率=税額控除前所得割額④
税額控除前所得割額④−税額控除額⑤=所得割額⑥
所得割額⑥+均等割額⑦+森林環境税額⑧=特別徴収税額⑨
特別徴収税額⑨−控除不足額⑩=差引納付額
又は住民税が年金から天引きされている方
→総所得金額−所得控除額合計=課税総所得金額
課税総所得金額×税率=税額控除前所得割額
税額控除前所得割額−税額控除額=所得割額
所得割額+均等割額+森林環境税=年税額
年税額−給与特別徴収税額−年金特別徴収税額−控除不足額=納付税額
※複数の徴収方法を併用して納付いただく場合もあります。
(注)
1 分離課税の所得がある場合は計算方法が異なります。
2 「税額控除額」は調整控除、配当控除、住宅借入金等特別税額控除、寄附金税額
控除、配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除等の控除額の合算額を記載してい
ます。
3 「控除不足額」は所得割額より控除することができなかった配当割額又は株式等
譲渡所得割額の控除の額のことです。
令和8年度から適用される主な改正点
◎給与所得控除の見直し
給与所得控除の最低保障額について、65万円(現行55万円)に引き上げ
◎特定親族特別控除の創設
大学生年代(19歳以上23歳未満)の子等の合計所得金額が95万円(給与収入160万円に相当)までは、親等が特定扶養控除と同額(45万円)の所得控除が受けられ、合計所得金額が95万円を超えた場合でも親等が受けられる控除の額が下表のとおり段階的に逓減する仕組みが導入されます。
| 親族等の合計所得金額 | 特定親族特別控除額 |
|---|---|
| 58万円超95万円以下 | 45万円 |
| 95万円超100万円以下 | 41万円 |
| 100万円超105万円以下 | 31万円 |
| 105万円超110万円以下 | 21万円 |
| 110万円超115万円以下 | 11万円 |
| 115万円超120万円以下 | 6万円 |
| 120万円超123万円以下 | 3万円 |
◎扶養親族等の所得要件の改正
| 扶養親族等の区分 | 合計所得金額 | |
|---|---|---|
| 改正後 | 改正前 | |
| 同一生計配偶者および扶養親族 | 58万円以下 | 48万円以下 |
| 配偶者特別控除の対象となる配偶者 | 58万円超133万円以下 | 48万円超133万円以下 |
| ひとり親に係る生計を一にする子(※) | 58万円以下 | 48万円以下 |
| 勤労学生 | 85万円以下 | 75万円以下 |
※ひとり親に係る生計を一にする子については総所得金額等
◎家内労働者等の所得計算の特例に係る控除額の引き上げ
家内労働者等の事業所得等から差し引く必要経費の最低保障額について、65万円(現行55万円)に引き上げ
令和6年度から適用される主な改正点
令和4年度から適用される主な改正点
◎住宅ローン控除の期間延長等
所得税の住宅ローン控除の適用者(※)について、所得税額から控除しきれなかった額を、所得税の課税総所得金額等の5%(最高9.75万円)の範囲内で個人住民税額から控除します。
また、所得税の住宅ローン控除については控除率を1%から0.7%に引き下げ控除期間を13年とし、省エネ住宅の場合の借入限度額を上乗せすることとなりました。
(※)住宅を取得等して令和4年から令和7年までの間に居住を開始した者
令和3年度から適用される主な改正点
◎給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替え
働き方の多様化を踏まえ、働き方改革を後押しする等の観点から、特定の収入にのみ適用される給与所得控除および公的年金等控除の控除額は一律10万円引き下げ、どのような所得にも適用される基礎控除の控除額が10万円引き上げられます。
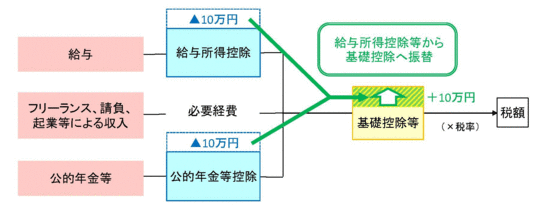
(財務省HPより)
◎給与所得控除の見直し
1.給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。
2.給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられます。
| 給与等の収入金額(A) | 給与所得控除額 | |
|---|---|---|
| 改正後 | 改正前 | |
| 162万5千円以下 | 55万円 | 65万円 |
| 162万5千円超 180万円以下 | (A)×40%-10万円 | (A)×40% |
| 180万円超 360万円以下 | (A)×30%+8万円 | (A)×30%+18万円 |
| 360万円超 660万円以下 | (A)×20%+44万円 | (A)×20%+54万円 |
| 660万円超 850万円以下 | (A)×10%+110万円 | (A)×10%+120万円 |
| 850万円超 1,000万円以下 | 195万円 | |
| 1,000万円超 | 220万円 | |
◎公的年金等所得控除の見直し
1.公的年金等所得控除額が一律10万円引き下げられます。
2.公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合、公的年金等控除額は195万5千円が上限とされます。
3.公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下の場合には一律10万円、2,000万円を超える場合には一律20万円が上記1および2の見直し後の控除額から引き下げられます。
| 公的年金等の収入金額(A) | 公的年金等所得控除額 | |||
|---|---|---|---|---|
| 改正後 | 改正前 | |||
| 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 | ||||
| 1,000万円以下 | 1,000万円超2,000万円以下 | 2,000万円超 | 区分なし | |
| 130万円以下 | 60万円 | 50万円 | 40万円 | 70万円 |
| 130万円超 410万円以下 | (A)×25%+27万5千円 | (A)×25%+17万5千円 | (A)×25%+7万5千円 | (A)×25%+37万5千円 |
| 410万円超 770万円以下 | (A)×15%+68万5千円 | (A)×15%+58万5千円 | (A)×15%+48万5千円 | (A)×15%+78万5千円 |
| 770万円超 1,000万円以下 | (A)×5%+145万5千円 | (A)×5%+135万5千円 | (A)×5%+125万5千円 | (A)×5%+155万5千円 |
| 1,000万円超 | 195万5千円 | 185万5千円 | 175万5千円 | |
| 公的年金等の収入金額(A) | 公的年金等所得控除額 | |||
|---|---|---|---|---|
| 改正後 | 改正前 | |||
| 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 | ||||
| 1,000万円以下 | 1,000万円超2,000万円以下 | 2,000万円超 | 区分なし | |
| 330万円以下 | 110万円 | 100万円 | 90万円 | 120万円 |
| 330万円超 410万円以下 | (A)×25%+27万5千円 | (A)×25%+17万5千円 | (A)×25%+7万5千円 | (A)×25%+37万5千円 |
| 410万円超 770万円以下 | (A)×15%+68万5千円 | (A)×15%+58万5千円 | (A)×15%+48万5千円 | (A)×15%+78万5千円 |
| 770万円超 1,000万円以下 | (A)×5%+145万5千円 | (A)×5%+135万5千円 | (A)×5%+125万5千円 | (A)×5%+155万5千円 |
| 1,000万円超 | 195万5千円 | 185万5千円 | 175万5千円 | |
◎基礎控除の見直し
1.基礎控除額が一律10万円引き上げられます。
2.合計所得金額が2,400万円を超えると、その金額に応じて控除額が逓減し、2,500万円を超えると、基礎控除は適用されなくなります。
3.上記1および2の見直しに伴い、前年の合計所得金額が2,500万円を超えると、調整控除が適用されなくなります。
| 個人の合計所得金額 | 基礎控除額 | |
|---|---|---|
| 改正後 | 改正前 | |
| 2,400万円以下 | 43万円 | 33万円(所得制限なし) |
| 2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 | |
| 2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 | |
| 2,500万円超 | 適用なし | |
◎所得金額調整控除の創設
1.給与等の収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合には、給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額が、給与所得の金額から控除されます。
・本人が特別障がい者に該当する
・年齢23歳未満の扶養親族を有する
・特別障がい者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する
控除額=(給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10%
2.給与所得および公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得および公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合には、給与所得(10万円を限度)および公的年金等に係る雑所得(10万円を限度)の金額の合計額から10万円を控除した残額が、給与所得の金額から控除されます。
控除額=(給与所得(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得(10万円を超える場合は10万円)-10万円
◎各種所得控除等を受けるための扶養親族等の合計所得金額要件等の改正
同一生計配偶者、扶養親族などの対象となる扶養親族等の合計所得金額要件がそれぞれ10万円引き上げられ、次の表のとおり改正されました。
| 扶養親族等の区分 | 合計所得金額要件 | ||
|---|---|---|---|
| 改正後 | 改正前 | ||
| 同一生計配偶者および扶養親族 | 48万円以下 | 38万円以下 | |
| 配偶者特別控除の対象となる配偶者 | 48万円超133万円以下 | 38万円超123万円以下 | |
| 勤労学生 | 75万円以下 | 65万円以下 | |
上記のほか、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額が55万円(改正前:65万円)に引き下げられています。
個人市県民税の非課税基準の金額についても10万円引き上げられます。
| 要件等 | 改正後 | 改正前 | |
|---|---|---|---|
| 障がい者、未成年者、寡婦およびひとり親に対する個人市県民税の非課税措置の合計所得金額要件 | 135万円以下 | 125万円以下 | |
| 均等割の非課税限度額の合計所得金額(非課税となる方) | 同一生計配偶者および扶養親族がない方 | 28万円+10万円 | 28万円 |
| 同一生計配偶者および扶養親族がある方 | 28万円×(1+扶養人数)+10万円+16.8万円 | 28万円×(1+扶養人数)+16.8万円 | |
| 所得割の非課税限度額の合計所得金額(均等割のみ課税される方) | 同一生計配偶者および扶養親族がない方 | 35万円+10万円 | 35万円 |
| 同一生計配偶者および扶養親族がある方 | 35万円×(1+扶養人数)+10万円+32万円 | 35万円×(1+扶養人数)+10万円+32万円 | |
ひとり親控除および寡婦(寡夫)控除に関する改正
すべてのひとり親家庭の子どもに対して公平な税制を実現する観点から、婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する「寡婦・寡夫・新たに控除対象となる未婚のひとり親」に対して、同一の「ひとり親控除」(控除額30万円)が適用されます。上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除(控除額26万円)が適用されますが、ひとり親控除・寡婦控除ともに、所得制限(合計所得金額が500万円以下)が設けられます。
※ひとり親控除・寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」などの記載がある方は対象外となります。
令和2年度以前の改正点について
令和2年度以前の改正点についてはこちら![]() (704KB)
(704KB)![]()
~納税通知書に関することや具体的な課税の内容について疑問等がある場合はお気軽に税務課へお問い合わせください~
 お問い合わせ先
お問い合わせ先
- 市民環境部 税務課
- 〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1 - Tel 0854-40-1034
- Fax 0854-40-1125
- zeimu@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。

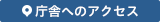

 妊娠・出産
妊娠・出産 子育て
子育て 学校・教育
学校・教育 結婚・離婚
結婚・離婚 住まい・引越し
住まい・引越し 就職・退職
就職・退職 高齢者・介護
高齢者・介護 お悔やみ
お悔やみ

 利用者別メニューから探す
利用者別メニューから探す







 お問い合わせはこちら
お問い合わせはこちら